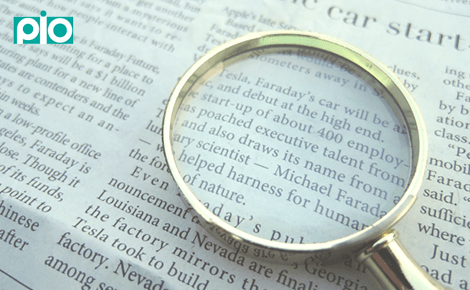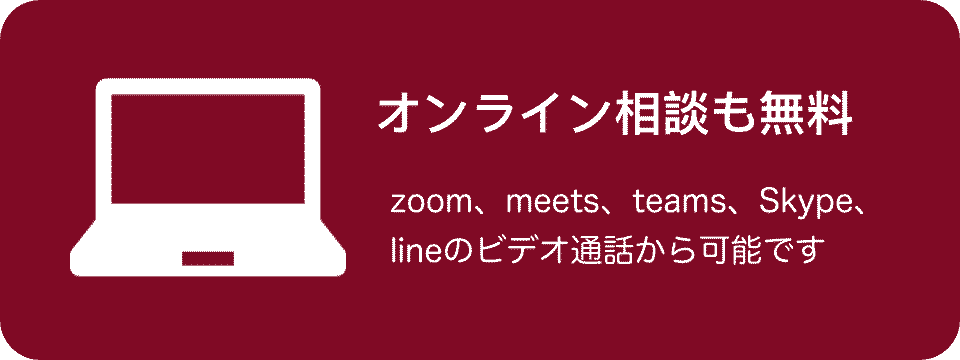SNSで誹謗中傷の被害にあったときの具体的な対処法とは?罰則や実例とともに紹介

TwitterやInstagramなどのSNSでは、特定の人に対する誹謗中傷が行われているのを目にすることがあります。芸能人や有名人に対して匿名で執拗に誹謗中傷をする悪質なケースも目立っています。
実際にSNS上の誹謗中傷が原因で被害者がうつ病になったり自殺に追い込まれたりする事例が報道されることも耳にするようになりました。
そこまでではなくても、誹謗中傷がインターネット上に残ることによって、就職活動や結婚など誹謗中傷を受けた人の将来の社会生活に支障をきたすおそれもあります。
そこで、SNS上で誹謗中傷を受けた場合にどのような対策をとる必要があるのか解説します。
ちなみに、逆にSNSの誹謗中傷で訴えられた場合は、こちらを参考にしてください。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。
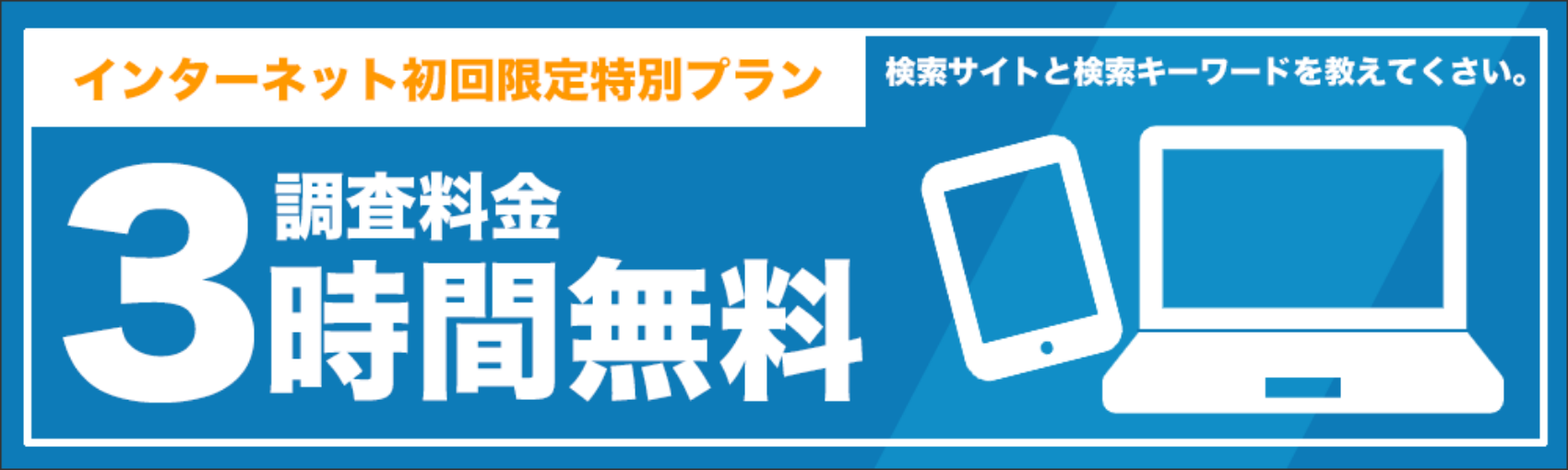
SNSでの誹謗中傷とは

SNS上での誹謗中傷にはどのような特徴があるのでしょうか。よくある事例とともに解説します。
SNSとは
SNSとは「Social networking service=ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略で、インターネット上で人々が交流するために提供されるサービスの総称です。匿名であったり、不特定多数のユーザーからコメントを書き込めたりするのがSNSの特徴です。
SNSに特別に細かい定義は存在しませんが、漠然とした解釈としては「交友関係を構築するインターネットサービス」ということになります。
誹謗中傷とは
誹謗中傷とは「誹謗」と「中傷」の二つからなる言葉。「誹謗」は悪口や陰口などの「そしり」を意味し、「誹」も「謗」も「そしる」を意味します。「中傷」は根拠のないことを言い、他人の名誉を傷つけること。「誹謗中傷」と合わせることで「いわれのない悪口」という解釈が一般的でしょう。
インターネットの人権侵害状況
総務省の支援事業「違法・有害情報相談センター」で受け付けている相談の件数は増加傾向にあり、2019年の相談件数は2010年の約4倍となっています。もっとも多い相談内容は「プライバシー侵害」、続いて「名誉・信用毀損」。プライバシー侵害は「住所、電話番号、メールアドレス等」、「写真、映像など肖像権侵害」、「リベンジポルノ」、「過去の犯罪記事」の順で、個人情報の具体的な相談が寄せされています。
被害を受けた書き込みが行われた場所は「ブログ・個人のHP」「SNS」「2・5ちゃんねるコピーサイト」「画像・動画共有サイト」「2・5ちゃんねる」の順番が多くなっていますが、具体的な相談作業の内訳ではSNSがもっとも多く、SNSの拡散性が人権被害を加速しているとも言えるでしょう。
SNSの変遷とサービスの特徴
SNSという言葉を日本で一般的にしたものが2004年にサービスを開始した日本発のSNS「mixi」。サービス開始当時は完全招待制でしたが、後に撤廃され、年齢、性別を自由に設定できるようになりました。匿名で不特定多数と交流できることから2010年にはユーザー数が2000万人のサービスとなりました。
このmixiに待ったをかけたのが「Facebook」。アメリカで2004年にサービスを開始、日本語でのサービス開始は2008年です。匿名性の高いmixiに対して、非匿名性を特徴として実名登録が基本。現実社会の延長線上にあることを意識したサービスです。
日記を交換するような濃密なつながりのmixiやFacebookと異なり、「つぶやき」でゆるいつながりの「手軽なSNS」として登場したのがTwitter、写真を不特定多数に公開し「(インスタ)映え」という言葉を生み出したInstagram、ショート動画の手軽さで「口パク」で急速に拡大したTikTokなど、様々なサービスが登場しています。
どのサービスも限定的に非公開にする機能はあるものの、基本は「不特定多数に向けた投稿を行い、不特定多数からコメントを貰う」サービスになります。
SNSは誹謗中傷の温床となりやすい
SNSには、TwitterやFacebook、Instagramなどさまざまな種類があります。このうち、TwitterやInstagramは匿名のアカウントを作成できることから、一般的に誹謗中傷の温床となりがちです。
また、SNSは短文で気軽に投稿できることから、他の利用者が特定の人に対して誹謗中傷をしているのを見た人がさらに便乗して、誹謗中傷が「炎上」しやすい傾向もあります。
SNSの誹謗中傷の定義とは

SNSでの誹謗中傷の定義について、批判との違いや、よくある事例を参考に、どのような行為が誹謗中傷となるのかを考えてみましょう。
誹謗中傷と批判の違い
誹謗中傷と差が見えにくいものが「批判」。「批判」はすでにある意見や主張に対して、欠点にあたる部分を指摘し、検討を加えて評価する行為です。これは批判対象者と批判する人が対等な関係で批判対象者に反論の余地を与えています。
「誹謗中傷」は対等ではなく、一方的に、改善の余地を与えないもの。「ブス」「存在がありえない」「逝ってよし」など人格を否定するような発言が中心になります。ただしポジティブな「批判」であっても、内容や口調によって誹謗中傷となってしまうケースもあるので、言葉を注意深く選ぶ必要があります。
SNSの誹謗中傷となる具体的ケース
SNSにおいて誹謗中傷となってしまう具体的なケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
・真実ではないことを吹聴する:いわゆるデマ。茨城県で起きたあおり運転の加害者の同乗者について、全く関係のない人があたかもその同乗者ではないかと拡散され、千通を超えるメッセージを受けるといった事件がありましたが、まさに誹謗中傷の事案です。
・性格や容姿を罵倒する:性格が暗い、つまらない、キモい、髪が汚いなど性格や容姿を口撃したり、否定したりすることは誹謗中傷です。
・脅す:SNS上でコメントが白熱し、エスカレートしたあげくに「殺す」「気を付けて歩けよ」などの脅しの表現は誹謗中傷に該当します。
・プライバシーを侵害する:コメント欄に個人の情報にかかる情報を掲載することは誹謗中傷にあたります。名前や住所、家族構成、学歴など様々なことが該当します。
・販売される商品の悪口を言う:誹謗中傷は個人だけが対象ではありません。企業が販売する商品を、根拠もないことで悪くいうことも誹謗中傷に該当します。
SNSでよくある誹謗中傷の例

SNSでよくある誹謗中傷としては、大きく分けて、相手の名誉を毀損するもの、相手を侮辱するもの、相手の個人情報やプライバシーをさらすものの3パターンがあります。
相手の名誉を毀損するもの
SNSにおける誹謗中傷によって、いわゆる名誉毀損が成立するのは、具体的な事実関係を指摘して相手の社会的評価を低下させた場合です。例えば、「Aさんは不倫をしている」とか「Bさんは社内の金を横領した過去がある」などというものです。重要なのは、具体的な事実を指摘したという点です。
具体的な事実関係を指摘したといえるかは、証拠さえあれば真偽を判定できるような内容であるかによって判断します。不倫をしていることや横領をしたことは、いずれも証拠さえあれば真実か否かを判断できる事柄です。
これに対し、例えば「Cさんはブサイクだ」とSNSで書き込まれた場合、不細工かどうかは主観に過ぎず証拠によって一義的に判断できるようなものではありません。このため、通常は名誉毀損とはなりません。
相手を侮辱するもの
刑法は、名誉毀損とは別に、人を侮辱することを刑事罰の対象としています。したがって、「Cさんはブサイクだ」といったSNSでの誹謗中傷は、名誉毀損にはならないとしても侮辱にあたる可能性はあります。このため、名誉毀損にあたらなければ違法ではないというわけではありません。
ただし、名誉毀損にはならない侮辱による誹謗中傷は、名誉毀損となる誹謗中傷と比較して加害者が支払うべき慰謝料の金額がかなり少なくなる傾向にあります。
相手の個人情報やプライバシーをさらすもの
SNS等での誹謗中傷では、相手の個人情報の公開を伴うことがあります。例えば、公開される個人情報としては、本名や出身地、住んでいる地域や子どもの学校名などがあります。
このほか、普通の人であれば秘匿しておきたいような情報が本人に無断で公にされることもありえます。例えば、病歴や生い立ちに関するものが典型的です。
個人情報は、SNSなど不特定多数の人が見る場所での公にされることは当然予定されていません。また、SNSは拡散力が高いため、多くの人に個人的な情報を知られることで被害者は普通の社会生活を送ることが難しくなる可能性があります。
このほか、個人情報だけでなく、身内との食事中の様子や部屋でくつろいでいる様子などといったプライベートな写真をSNS等で拡散されるケースもあります。この場合には、プライバシーの侵害とともに、肖像権の侵害も問題となることがあります。
SNSの誹謗中傷による責任と罰則

実際に誹謗中傷を行った場合に課される刑罰について確認しましょう。大きく、刑事責任と民事責任に分かれており、それぞれで内容や状況に応じて対応が異なります。
刑事責任
刑事責任となる誹謗中傷は以下が該当します。
・名誉毀損罪:他人の名誉を傷つける行為。刑法230条で定義されており、「公然」と「事実を摘示」して「名誉を毀損」する行為。公然とは「不特定多数が知る可能性がある」状態。事実の摘示とは真実かどうかがわからない情報を伝えることですので、SNSで真実かどうかわからないことを発信すると名誉毀損罪で訴えられる可能性があります。
・侮辱罪:仮に真実であったとしても、不特定多数が知る可能性のある公然で侮辱すると刑
法第231条に該当します。馬鹿、頭が悪いといった表現でも、公然であれば成立します。
・信用毀損罪・業務妨害罪:虚偽の風説を流すことで人の信用を失墜させた、営業妨害を行った場合は刑法第233条によって信用毀損罪、業務妨害罪が問われます。信用毀損の信用は支払い能力や支払い意思などの経済的な信用を指します。
・脅迫罪:殺すぞ、やってやる、など生命や、身体、名誉、財産に対して害を加える旨を告知する行為は、刑法第222条の脅迫罪に該当します。
・強要罪:「アカウントを閉じろ!」などの発言は、脅迫や暴行によって義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすることになり、刑法第223条の脅迫罪が適用されます。
民事責任
誹謗中傷を行うと、民法第709条を根拠として、被害を受けた相手に損害賠償の責任、不法行為責任が発生します。不法行為責任は故意でも過失でも刑事責任とは別に民事責任を果たす必要が生じることを言います。
損害賠償:誹謗中傷を受けたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料や、風評被害による売上減少などの損害について賠償しなければなりません。
名誉回復措置:不法行為は通常、金銭によって賠償することが原則です。しかし、名誉毀損は「名誉を回復するのに適当な処分」が求められ、名誉を回復するために謝罪広告などを出すことが命じられる場合があります。
SNSで誹謗中傷を受けた場合の対処法

SNSで誹謗中傷を受けた場合、被害を最小限にしたければどれだけ迅速に対応できるかが鍵になります。
SNSでは短期間の間に大量に誹謗中傷コメントが拡散されます。SNS上の誹謗中傷が収束しても、匿名掲示板やブログなど他のwebサイト上にSNSに投稿された内容が転載されることとなれば将来にわたり被害が継続するリスクがあります。
また、SNS上の誹謗中傷の加害者を特定するためにはプロバイダから投稿者の情報を開示してもらう必要があります。しかし、加害者の特定に必要となる接続ログは通常3ヶ月から1年程度の短い期間で抹消されてしまいます。接続ログが抹消されると、加害者を特定することは非常に困難になるため、被害回復が十分に図られないリスクがあります。
誹謗中傷コメントの削除
SNSにおいて誹謗中傷を受けた場合には、まず問題の投稿を抹消してもらう必要があります。加害者が特定できていない場合には、誹謗中傷が投稿されたSNSの運営会社に対して名誉毀損等にあたることを説明して投稿の抹消を求めます。
SNSの代表であるTwitterでは、「Twitterルール」として攻撃的な行為・嫌がらせ、ヘイト行為、自殺や自傷行為の助長や扇動、個人情報の無断開示などを明確に禁止しています。
したがって、Twitter社に対して誹謗中傷ツイートの抹消を求める場合には、Twitterルールに記載された禁止行為のどれに該当するかを明示し、問合せフォームや報告機能などを用いて削除を求めることになります。
また、誹謗中傷のコメントは投稿者によって削除される可能性があるため、発見した場合には投稿のURLを記録するだけでなく、投稿自体のスクリーンショットも保存しておく必要があります。
その際、投稿内容、投稿者のアカウント名、投稿日時、投稿のURLのすべてが同じ画面内に保存されるような形式で画像を保存しておくことがポイントです。
誹謗中傷の加害者の特定
誹謗中傷の削除と一緒に進められることが多いのは、誹謗中傷をした加害者を特定する手続です。TwitterやInstagramなどのSNSは匿名で投稿ができるため、加害者の氏名や住所を特定するためには法的な手続きを踏む必要があります。
SNSは会員制の交流サイトであることから、コンテンツ・プロバイダ(SNSの運営事業者)にアカウントの登録者情報の開示請求をすればよいと思われるかもしれません。
しかし、SNSの運営事業者にとって登録者の情報は個人情報保護法によって保護される個人情報です。このため、登録者に無断で被害者に開示することは難しいのが一般的です。このため、法律に定められた手続を踏む必要があるのです。
SNSでの誹謗中傷などインターネット上のトラブルにおいて、投稿者の個人情報の開示を受けるための法的根拠はプロバイダ責任制限法という法律です。誹謗中傷の被害を受けた人が加害者の個人情報を入手するためには、プロバイダ責任制限法に基づいて請求をする必要があります。この請求を、「発信者情報開示請求」と呼びます。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行う場合、次の2段階の手続が必要です。
SNS運営事業者に対するIPアドレスの開示請求
IPアドレスとは、インターネット上の通信に用いられる機器に割り振られる番号であり、通信相手を識別するものです。このため、インターネット上の住所と呼ばれることもあります。
SNS上の誹謗中傷のコメントについては、その投稿と投稿者を紐付けるIPアドレスが存在します。このIPアドレスはコンテンツ・プロバイダとも呼ばれるSNSの運営事業者(X(元Twitter社)など)が保有しています。
そこで、まずSNSで誹謗中傷の被害を受けた場合には、問題の投稿に関するIPアドレスの開示をSNS運営事業者に求める必要があります。
コンテンツ・プロバイダによっては裁判所を通さない請求でIPアドレスを開示することもあります。もっとも、多くのケースでは裁判所への仮処分申立てによってIPアドレスの開示がされることになります。
仮処分申立てをしてから実際にIPアドレスの開示を受けられるまでは、一般的に1〜2ヶ月程度です。ただし、これはあくまでもコンテンツ・プロバイダが日本の事業者である場合の目安です。
SNSにおいては多くのケースでコンテンツ・プロバイダは海外の事業者です。海外のコンテンツ・プロバイダからIPアドレスの開示を受けるためには、3〜4ヶ月程度の期間を要することが通常です。
また、海外への送達が必要になる関係上、日本国内のプロバイダに対する請求よりも手続上の負担は重くなります。
インターネット・サービス・プロバイダに対する契約者情報の開示請求
次に、SNSを運営する事業者から開示されたIPアドレスを、WHOISというインターネットで誰でもアクセスできるシステムで検索します。そうすると、その投稿をする際に投稿者が利用したインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)を割り出すことができます。
ISPとは、インターネット接続サービスを提供している事業者です。有名なところでは、OCNなどがあります。この他、携帯電話会社もISPにあたります。
ISPが有料サービスである場合には、ISPは誹謗中傷の投稿者と利用契約を締結しているはずです。したがって、ISPは誹謗中傷の投稿者の個人情報を保有しています。
そこで、ISPに対してSNS上で誹謗中傷の投稿をした加害者の氏名や住所などの情報を開示するように請求することになります。
なお、ISPに対する加害者の個人情報の開示請求は、現時点では、裁判所に通常の訴訟を提起する必要があります。このため、ISPから加害者の個人情報の開示を受けられるまでには、6ヶ月〜1年程度の期間を要することになります。
なぜ裁判手続きが必要となるのかというと、ISPにとって契約者の情報は、個人情報保護法の観点から原則として本人の同意を得ずに開示できない情報であるためです。このため、ISPは、開示を認める判決がないかぎり開示に応じないというのが現状です。
加害者に対する慰謝料請求
加害者の個人情報が特定できたら、次に加害者本人に連絡して慰謝料の支払いや今後同様の誹謗酋長を行わないことの誓約などを求めることになります。悪質な事例では刑事告訴を検討することもあります。
なお、初めから刑事告訴を視野に入れている場合には、上で説明したISP等に対する発信者情報開示請求の手続を省略できる可能性があります。警察の捜査によって、加害者の情報が判明することがあるためです。
インターネット上の誹謗中傷に対する国の取り組み

上で説明したように、SNS等のインターネット上の誹謗中傷に関しては加害者を特定して慰謝料請求等の権利を行使するまで非常に多くの手間がかかります。
一方で、インターネット上の誹謗中傷に関しては、裁判所が名誉毀損にあたることを認めたとしても慰謝料額は100万円前後の低い金額に抑えられることが一般的です。
このため、弁護士費用を支払うと赤字になることもあり、被害者が泣き寝入りする結果となりやすいことが問題視されています。このような現状を踏まえ、総務省は、発信者情報開示請求の手続を簡素化するため2020年4月から「発信者情報の在り方に関する研究会」を開催し、制度の変更を検討しています。
2020年12月には「最終とりまとめ」が公表されています。この中では、発信者情報開示請求のための特別の裁判上の手続を創設し、一回の手続で迅速に投稿者を特定できるようにする方向性が打ち出されています。
したがって、今後は、SNSで誹謗中傷をした加害者の特定について、裁判所を通した2段階の手続を踏むことなく、SNS運営事業者(コンテンツ・プロバイダ)とISP(インターネット・サービス・プロバイダ)のそれぞれから、迅速に個人情報の開示を受けられる可能性があります。
もっとも、「発信者情報の在り方に関する研究会」による最終とりまとめに従って、実際の法整備がなされるまでにはまだ時間を要することになります。このため、当面は上で説明したような2段階の発信者情報開示請求が必要となる状況は続くでしょう。
総務省が推奨する具体的な対処法
実際に誹謗中傷を受けた場合、どのようにしたら良いのでしょうか。総務省では「#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃ、SNSじゃない!)」をスローガンとして、具体的な方法を提示しています。
引用:総務省『SNS等での誹謗中傷』
身の危険を感じる場合
SNSの誹謗中傷に身の危険を感じる書き込みがあった場合の処置:最寄りの警察署や都道府県警察本部のサイバー犯罪窓口へ連絡します。
賠償を求めたい場合
SNSの誹謗中傷を書き込んだ人に賠償等を求めたい場合の処置:弁護士、または法テラスへ相談します。
連絡先:法テラス
まず削除したい場合
SNSの誹謗中傷を迅速に自分で削除依頼をする
SNSの誹謗中傷を自分で削除依頼できないので依頼したい
連絡先:「誹謗中傷ホットライン」(セーファーインターネット協会)
まとめ
SNS等において悪質な誹謗中傷を受けた場合には、早期に法的措置をとった方がよいことが多いといえます。
SNSの誹謗中傷は不特定多数の人が見ることができるため、他の利用者が誹謗中傷に便乗して「炎上」しやすい傾向にあります。このとき、被害者が「法的措置を講ずる」旨を公表するなど毅然とした対応をとることで、炎上を防止できる可能性が高まります。
興信所においては、加害者に結びつくいくつかの手がかりを元にしてSNSでの誹謗中傷の加害者を突き止める調査ができることがあります。
確実に相手を特定したい場合や、裁判によらず早く相手の情報を入手したい場合、加害者につながる手がかりはあるものの法的な手続では加害者の個人情報の開示が難しいような場合には、興信所などに調査を依頼することが一つの選択肢になるかもしれません。

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行調査専門 Y.K
浮気・素行調査のプロフェッショナル。調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。
関連タグ: 誹謗中傷

探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。