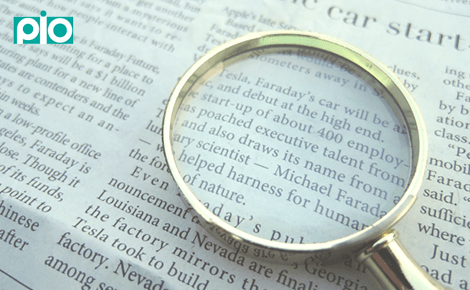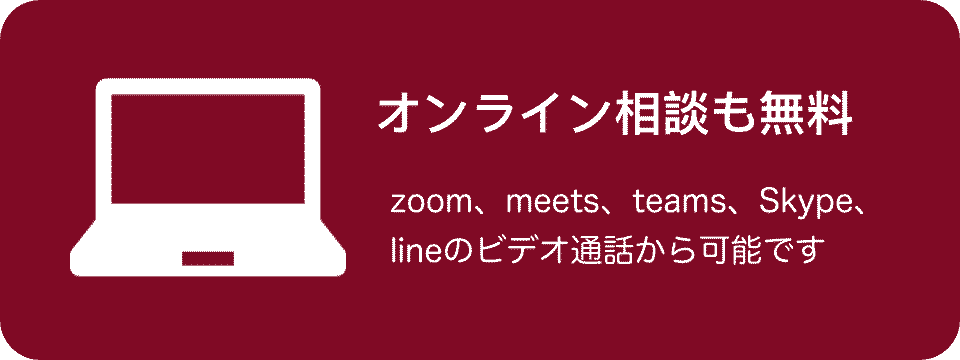業務上横領は少額でも捕まる可能性はある?物品の横領についても解説

業務上横領は、金額の大小に関わらず犯罪となる可能性があります。本記事では、少額の横領や物品の横領についても詳しく解説します。
他人や会社の財産(金銭や物品)を無断で私的に流用すると、「横領罪」として刑事責任を問われる可能性があります。場合によっては逮捕に至ることもあります。一般的に報道されるのは高額な横領事件が多いため、少額の横領は見過ごされがちですが、実際はどうなのでしょうか。
本記事では、少額でも横領罪が成立するケースや、物品の横領に関する法的解釈、さらに横領を犯してしまった場合の対処法などについて詳細に解説していきます。業務上横領のリスクと法的責任について理解を深めていただければ幸いです。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。
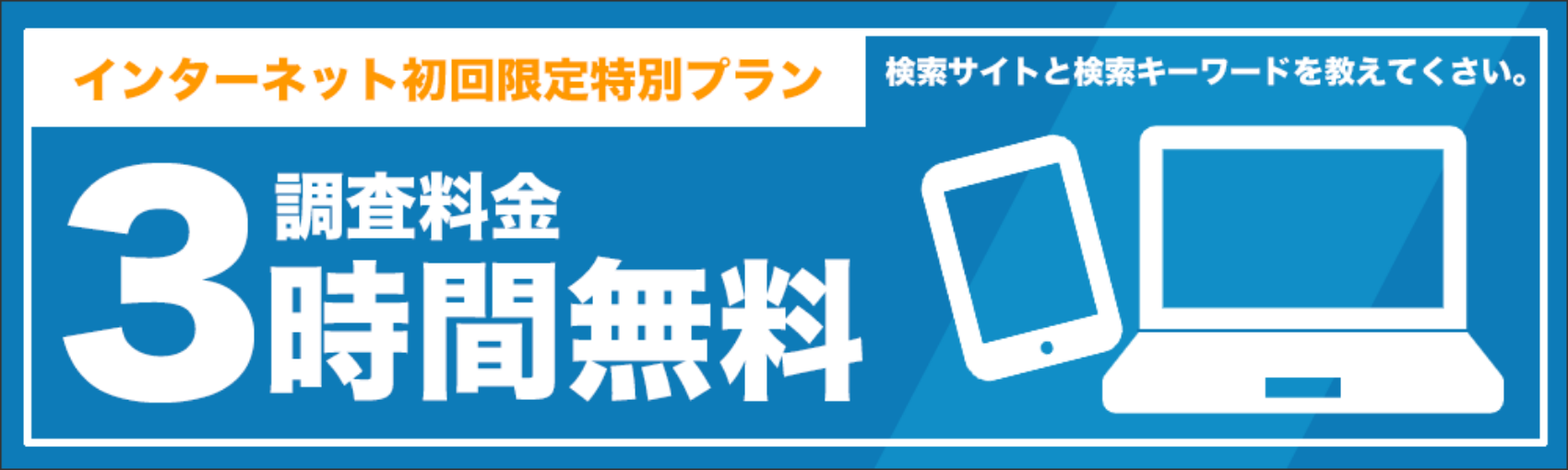
目次
業務上横領罪について知ろう
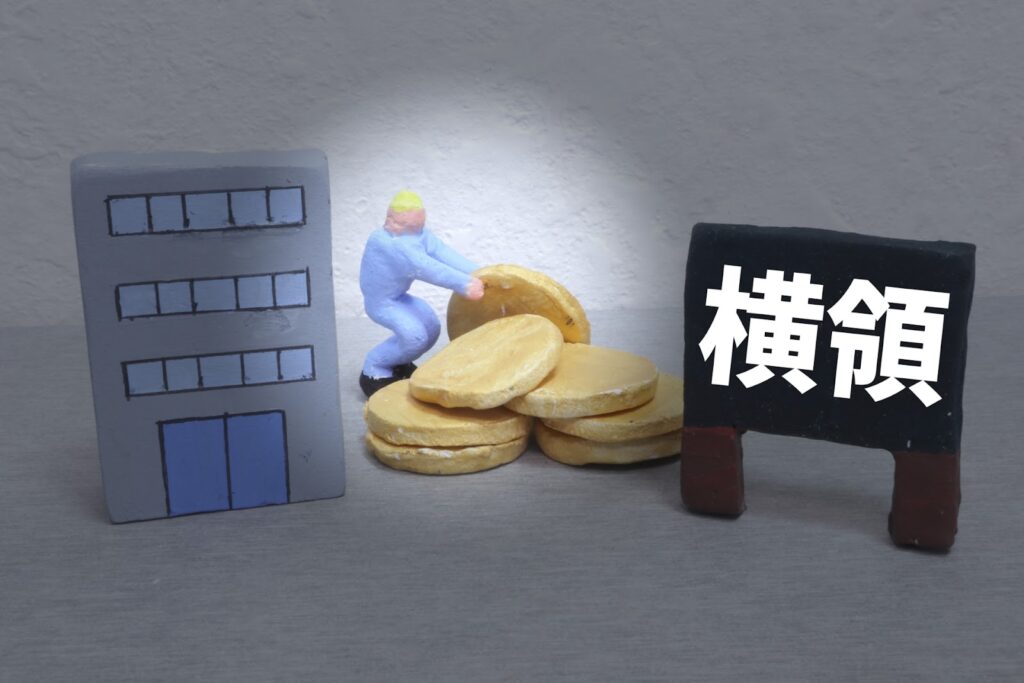
まずは、業務上横領罪について理解していきましょう。
業務上横領罪とは
業務上横領罪とは、刑法第253条に、定められている犯罪です。業務上横領罪が成立する要件には以下のようなことが挙げられます。
- 処罰の対象者は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者
- 仕事のように反復継続して実施していることが対象
- 業務関係のある他人から自分が管理や保管を委託されている物
要件に注目すると、業務上の関係が前提にあることが分かります。さらに、横領罪は「金銭」をイメージされることが多いですが、それ以外の他人から自分が管理や保管を委託されている物も含まれます。「金銭」に限らず、財産価値のある有体物を指すため、会社が管理している商品や物品を自分のものにしてしまった場合に刑に処されます。
業務上横領罪の刑罰の重さ
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。これは刑法第252条の「単純横領罪」の刑罰である5年以下の懲役と比べて重くなっています。企業と従業員で交わした契約に違反した責任は重く、刑罰の長さが信頼関係を裏切ったことの重大さを表しています。
業務上横領罪で逮捕されるケース

では具体的にどのようなケースが業務上横領罪となるのか、逮捕の可能性があるケースをいくつか紹介します。
少額でも逮捕のリスクはある
業務上横領は、金額の多寡に関わらず犯罪行為です。少額であっても、会社が被害届を出せば逮捕される可能性があります。ただし、実際には金額によって対応が異なることがあります。
金額による対応の違い
一般的に、横領額が200万円未満の場合、本人が事実を認め、身元が安定していれば、逮捕されずに在宅事件として扱われることが多いです。一方、数千万円以上の場合は逮捕される可能性が非常に高くなります。
物品の横領も対象となる
業務上横領は金銭に限らず、会社の物品を私的に使用したり売却したりする行為も含まれます。例えば、会社の備品を無断で持ち出して売却するなどの行為も業務上横領罪に該当します。
逮捕を避けるための対応
逮捕を避けるためには、会社との示談交渉が重要です。被害弁償や謝罪など、誠意ある対応を行うことで、会社が被害届を取り下げる可能性があります。ただし、示談が成立しても、金額が大きい場合は逮捕されるリスクが残ります。
業務上横領は、たとえ少額であっても重大な犯罪です。会社の信頼を裏切る行為であり、キャリアに大きな影響を与える可能性があります。不正な行為は絶対に避け、疑問がある場合は上司や専門家に相談することが重要です。
業務上横領罪となる判断の分かれ目は?

単純横領罪は業務上横領罪に比べ要件が多く、判断しづらい犯罪といえます。業務上横領罪が成立する判断について紹介しています。
営利の目的があるかどうか
業務上横領罪は、必ずしも営利目的の活動に限定されません。判断の基準となるのは、その行為が反復継続して行われる「業務」の一環であるかどうかです。
例えば、会社員が会社の資金を私的に流用する典型的なケースだけでなく、非営利団体や学校のPTA、保護者会などでの横領行為も業務上横領罪に該当する可能性があります。これらの団体での活動も、法的には「法規・慣習・契約などによって同種の行為を反復すべき地位にもとづく事務」と解釈され、業務性を帯びていると判断されるためです。
したがって、営利目的であるかどうかは業務上横領罪の成立に直接関係しません。重要なのは、その人が慣習や規約に従って特定の事務に継続的に従事しているかどうかです。この条件を満たせば、単純横領罪ではなく、より重い罰則が科される業務上横領罪として処罰される可能性が高くなります。
少額の横領であっても、それが業務の一環として行われた場合は業務上横領罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。また、金銭だけでなく、会社の物品を私的に使用したり売却したりする行為も業務上横領罪に該当する可能性があります。
責任者であるかどうか
業務上横領罪の成立には、委託信任関係が前提となるため、責任者であるかどうかは重要なポイントです。ただし、単に役職や立場の名称だけでなく、実質的な委託信任関係の有無が判断基準となります。
委託信任関係とは、会社の責任者(他人)から信頼を受け、物の保管や管理を任されている状況を指します。
境界線となる例
- 企業のプロジェクトや店舗運営を任されている責任者が売上金を横領した場合 → 業務上横領罪が成立
- 現場で会計や接客を担当するアルバイトやパート従業員が売上金を盗んだ場合 → 窃盗罪として扱われる可能性が高い
アルバイトやパート従業員の場合、通常は委託信任関係が成立していないと考えられるため、業務上横領罪ではなく窃盗罪として扱われる傾向があります。
法定刑の比較
- 業務上横領罪:10年以下の懲役
- 窃盗罪:10年以下の懲役または50万円以下の罰金
窃盗罪の方が罰金刑の選択肢があるため、一見すると軽く感じるかもしれません。しかし、懲役刑の上限は同じであり、どちらも重大な犯罪として扱われます。
重要なのは、役職や立場に関わらず、他人の信頼を裏切る行為は避けるべきだということです。少額であっても、業務上の立場を利用した横領行為は犯罪となる可能性が高いため、絶対に行ってはいけません。
業務上横領罪の成立ポイント
業務上横領罪の成立には、単なる”着服”だけでなく、”不法領得の意思”が重要なポイントとなります。不法領得の意思とは、他人の物を自分のものとして扱う意思のことを指します。
以下のような行為は、不法領得の意思があると判断され、業務上横領罪が成立する可能性が高くなります。
- 売却:会社の商品を無断で外部に販売し、利益を得る行為
- 費消:会社の物品を私的に使用したり、使い果たしたりする行為
- 拐帯:会社の物品を持ち逃げする行為
例えば、会社から信任を受けている管理者が自社の商品を外部に横流しし、謝礼を受け取った場合、商品自体は自身のものにしていなくても、不法領得の意思があると判断される可能性があります。
特に売却は金銭的利益を目的としているため、不法領得の意思が最も明確に表れる行為といえます。費消は、会社の物品を私的に使用して減少させたり、すべて使い果たして失くしたりすることを指します。拐帯は、会社の物品を無断で持ち出し、返還する意思がない状態を指し、悪質な犯罪とされます。
重要なのは、これらの行為が少額であっても業務上横領罪が成立する可能性があるということです。会社との信頼関係を裏切る行為は、金額の大小に関わらず、法的に重大な結果をもたらす可能性があるため、十分な注意が必要です。
横領するとどんなことが起きるのか

では、横領することでどんな処罰になるのでしょうか。一般的に、他人や会社の財産を横領すると「横領罪」という罪に問われることになりますが、それ以外にもさまざまな弊害が発生します。横領することでどのようなことになるのか、詳しく見ていきましょう。
懲戒解雇処分を受ける
業務上横領が発覚した場合、金額の多寡に関わらず懲戒解雇処分を受ける可能性が高くなります。横領は会社に対する重大な背信行為であり、雇用関係の継続を困難にする行為とみなされるためです。
例えば、以下のような判例があります。
- 信用金庫の従業員による1万円の横領でも懲戒解雇が有効と判断された事例
- 電鉄会社の助役による横領行為に対する懲戒解雇が無効とされた事例(ただし立証不十分が理由)
なお、懲戒解雇の有効性は、以下の点を考慮して判断されます。
- 就業規則に明確な懲戒解雇事由が定められているか
- 横領の金額や回数
- 従業員の職位や担当業務
- 会社の信頼を裏切る程度
- 反省の態度
物品の横領についても同様に扱われ、金銭的価値に応じて判断されます。
ただし、懲戒解雇を行う際は適正な手続きを踏む必要があります。具体的には、従業員に弁明の機会を与えることや、就業規則に定められた手続きを遵守することが重要です。これらの手続きを怠ると、たとえ横領行為が事実であっても、懲戒解雇が無効とされるリスクがあります。
横領が発覚した場合、会社は慎重に事実関係を調査し、適切な手続きを踏んだ上で懲戒処分を決定することが求められます。
刑事告訴される
業務上横領が発覚すると、会社から刑事告訴される可能性があります。業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立し、10年以下の懲役に処されます。
たとえ少額であっても、横領は犯罪行為であり、刑事事件化するリスクがあります。実際に、550円の着服で懲戒解雇が有効と認められた裁判例や、1万円の着服で懲戒解雇が有効とされた高裁判決などがあります。
横領の金額が多額になると、実刑判決を受ける可能性も高くなります。たとえば、顧客から預かったギター6本(177万円相当)を横領して質に入れた楽器修理会社経営者は、被害弁償をしていないことなどから執行猶予のつかない懲役1年半の実刑判決を受けています。
このように、業務上横領は少額でも刑事告訴され、有罪判決を受けるリスクがあるのです。会社の金品を不正に着服した場合、刑事責任を問われる可能性が十分にあることを認識しておく必要があります。
解雇予告手当や退職金が支給されない
横領行為が発覚した場合、懲戒解雇となる可能性が高く、通常の退職とは異なる扱いを受けることがあります。
まず、解雇予告手当については、原則として支払う必要がありますが、横領のような重大な非行の場合、労働基準監督署の認定を受けることで支払いを免除される可能性があります。ただし、横領の事実を従業員が否認したり、明確な証拠がない場合は、認定が下りないこともあるため注意が必要です。
退職金に関しては、就業規則や退職金規程に不支給事由が明記されていることが前提となります。その上で、会社財産の横領は、従業員の著しい背信行為とみなされ、退職金の全額不支給が認められる可能性が高いです。ただし、私生活での犯罪行為の場合は全額不支給が違法とされる判例が多いため、業務上の横領とは区別して考える必要があります。
なお、金額の多寡にかかわらず、横領行為は懲戒解雇の対象となり得ます。特に、経理係や支店長など、職務上お金を扱う立場にある場合は、より厳しい判断がなされる可能性があります。
ただし、懲戒解雇や退職金の不支給を行う際は、適切な手続きを踏むことが重要です。事実関係の十分な調査や、従業員への弁明の機会の提供を怠ると、後に処分が無効とされるリスクがあります。横領行為は、たとえ少額であっても、雇用関係や経済的側面に重大な影響を及ぼす可能性があるため、決して軽視できない問題です。
少額の横領で逮捕される可能性はあるのか

窃盗などの場合には、少額であることや初回であることを理由に示談にするというケースがありますが、委託された財産を悪用するという性質上、横領は窃盗罪などと比較しても悪質性が高く、処罰される対象に感じる方も多いかと思います。そこで、少額の横領ではどのようになるのか、ここではいろいろな視点で確認していきましょう。
少額でも刑事告訴される可能性は十分にある
業務上横領は、金額の多寡にかかわらず犯罪行為として扱われる可能性があります。実際に、過去の判例では550円や1,100円といった少額の着服でも懲戒解雇が有効とされたケースがあります。
刑事告訴されるかどうかは、主に以下の要因に左右されます。
- 被害企業の方針:会社が被害届を提出するかどうかが重要です。
- 横領の手口と頻度:計画性や反復性がある場合は重く見られます。
- 加害者の態度:真摯な反省と被害弁償の意思が重要です。
- 示談の成立:被害企業との示談が成立すれば、刑事告訴を回避できる可能性が高まります。
ただし、少額であっても刑事告訴される可能性は十分にあります。特に、信頼関係を裏切る行為として厳しく対処される傾向にあります。
横領が発覚した場合、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。示談交渉や被害弁償など、早期の対応が刑事告訴のリスクを軽減する可能性があります。
金額によっては許されることも
横領してしまった場合でも、その後の行動次第では(即時返金や謝罪等)許してくれるというケースも存在します。ただし、これは加害者と被害者の信頼関係や、横領後の対応、横領の金額が比較的小規模であるなど、様々な要因がかかわってくるため、どのケースでも当てはまるわけではありません。
横領後の姿勢やスピード感が大切になります。なぜ横領行為をしてしまったのかに対してしっかりと向き合い、すぐに謝罪をする、損害賠償を行う、示談交渉を行うなどの行動を早めに行うようにしましょう。一度崩れてしまった信頼関係を再構築していくことは簡単なことではありません。しかし、真摯に向き合っていくことで金額によっては許されることもあるでしょう。
社会的制裁や処分を受ける可能性がある
少額の横領であっても、刑事告訴されない場合でも懲戒解雇や他の企業への風評被害、社会的地位の失墜など、社会的制裁を受ける可能性は非常に高いです。特に懲戒解雇となった場合、その後の転職活動が大きく制約されることが考えられます。解雇の理由を次の会社に正直に伝える必要があり、これが転職の際に大きな障壁となることが多いです。そのため、少額の横領であっても、軽視せずに深刻な結果を招く可能性があることを認識しておくべきです。
業務上横領罪の金額に応じた量刑の目安

ここでは、具体的な金額を目安に業務上横領罪の量刑の目安を紹介していきます。あくまで目安となるため、実際の量刑とは異なることを理解しておきましょう。
| 被害金額100万円以下 | 執行猶予 |
| 被害金額500万円 | 2年前後の実刑 |
| 被害金額1000万円 | 2年6か月の実刑 |
| 被害金額3000万円以上 | 3年以上の実刑 |
例を挙げながら、金額に応じた量刑について、理解を深めていきましょう。
被害金額100万円以下
| 被害金額42万円 | 示談なしで懲役1年6月執行猶予3年 |
| 被害金額85万円 | 示談なしで懲役1年6月執行猶予3年 |
| 被害金額100万円 | 示談が成立し懲役1年6月執行猶予3年 |
加害者は前科があったのかどうか、横領発覚後の示談(弁償)の有無など、様々な状況が考慮されたうえで刑罰が判断されます。過去に行われた判例なども参考にしながら、量刑が決まっていきます。
被害金額100万円以上1000万円以下
| 被害金額230万円 | 示談なしで懲役1年6月実刑 |
| 被害金額493万円 | 示談なしで懲役2年実刑 |
| 被害金額715万円 | 示談なしで懲役2年6月実刑 |
100万円以上の大きな金額になってくると、示談が成立しないことが多い傾向にあります。さらに100万円以下と異なり、執行猶予ではなく実刑となることが分かります。
被害金額が1000万円以上
| 被害金額1700万円 | 前科があるものの示談が成立懲役1年8月実刑 |
| 被害金額約1700万円 | 示談なしで懲役2年6月実刑 |
| 被害金額2350万円 | 示談なしで懲役3年実刑 |
| 被害金額4000万円 | 示談なしで懲役3年6月実刑 |
1000万円以上の日が金額になると、示談成立があったとしても実刑となることが多いです。なお、懲役1年6月執行猶予3年は、3年間の執行猶予期間中に刑事事件を起こさないことが重要となります。もしも、3年以内に刑事事件を起こした場合には、新しく起こした刑事事件の懲役期間に加えて刑に服することになります。
会社で横領してしまった場合の対処法

ここでは、万が一横領を行ってしまった場合の対処法について解説していきたいと思います。
弁護士に相談し、すぐに謝罪、交渉の準備をする
横領行為を行ってしまった場合、まず弁護士に相談し、今後の対応について助言を求めることが重要です。会社に発覚する前に自己申告することで、最悪の事態を回避できる可能性があります。後から発覚すると悪質性が高まり、刑事告訴される可能性が高くなります。また、懲戒解雇や退職金不支給などの社内制裁も厳しくなる可能性があります。
弁護士を介することで、冷静な判断と適切な対応が可能になります。隠蔽や個人での対処は避け、誠実に対応することが重要です。これにより、被害の拡大や事態の悪化を防ぐことができます。
自己申告して責任を取る
横領を行った時点で、自ら経緯や状況を素直に申告し、早期に問題解決を図ることが重要です。横領罪は被害者の告訴がなければ刑事事件に発展しないケースもあるため、発覚までに時間がかかることがあります。
しかし、発覚しなければ大丈夫と考えるのは危険です。少額から始まっても、最終的に多額の横領に発展するケースも少なくありません。金額が大きくなり期間が長くなるほど、罪は重くなります。
日本の刑法では、横領罪の法定刑は5年以下の懲役で、時効は5年です。また、会社も行政処分を受ける可能性があります。早期の自己申告は、被害者に対する誠意を示し、結果的に処分を軽減できる可能性があります。
自己申告により、民事上の賠償責任を負う可能性はありますが、刑事告訴を回避できる可能性も高まります。横領の事実を隠蔽せず、誠実に対応することが、最善の対処法といえるでしょう。
まとめ
今回は少額の横領で逮捕される可能性と、横領してしまった場合の対処法について解説させて頂きました。結論を言ってしまうと、いかなる場合でも横領罪は犯罪であり、「逮捕される可能性」があります。不正が見つからない限りバレないというところがあるものの、発覚した際には社会的責任を取るべき不正行為であるということを理解しておくことが重要です。
まずは横領について疑問に感じたことがあれば、弁護士に相談してみるのもいいと思います。

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K
調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。
関連タグ: 業務上横領

探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。