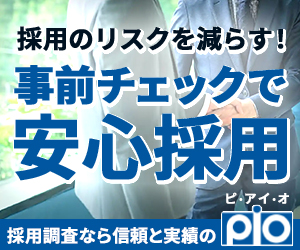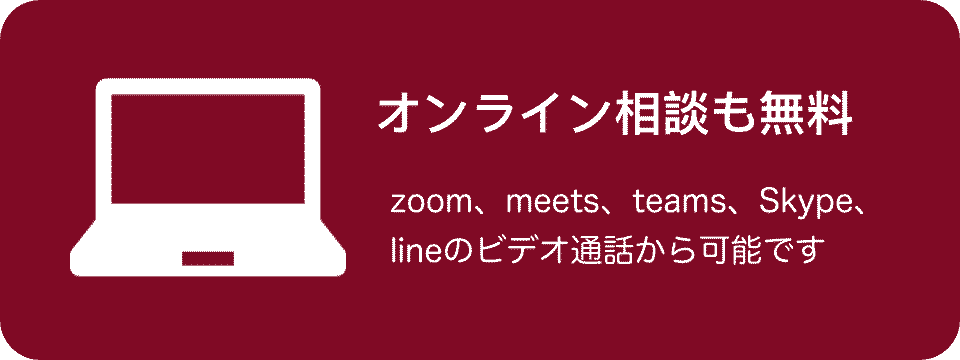【採用調査】今すぐ知りたい!費用と法律の真実とは?

「採用調査を依頼したいけど、費用がどれくらいかかるのか心配…」「法律に違反しないか不安…」と感じている方もいるでしょう。
採用調査は企業にとって重要なプロセスですが、その詳細についてはなかなか知る機会が少ないものです。
この記事では、採用調査に関心がある方に向けて、
– 採用調査の基本と目的
– 採用調査で確認する項目
– 採用調査の進め方
– 採用調査の費用について
上記について、解説しています。
採用調査に関する悩みや疑問を解消することで、安心して調査を進めることができるでしょう。
情報を事前に知っておくことで、適切な判断ができるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
PIO探偵事務所は興信所探偵社として業歴53年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽にPIO探偵事務所までご相談下さい。
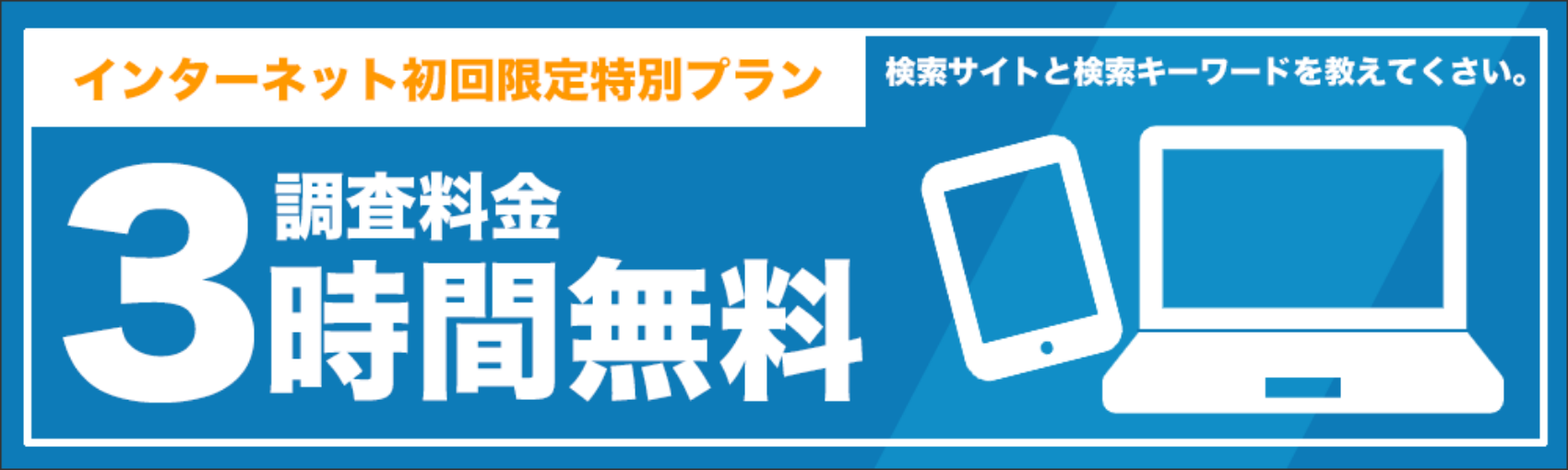
目次
- 1 採用調査の基本と目的
- 2 採用調査と関連用語の違い
- 3 採用調査で確認する項目
- 4 採用調査の進め方
- 5 採用調査の費用について
- 6 海外と日本における採用調査の違い
- 7 採用調査に関するよくある質問
- 7.1 Q1. 採用調査とは何ですか?
- 7.2 Q2. 採用調査を行う際に候補者の同意は必要ですか?
- 7.3 Q3. 前職の勤務態度や退職理由を確認しても良いですか?
- 7.4 Q4. SNS(ソーシャルメディア)の投稿内容を採用調査に利用しても良いですか?
- 7.5 Q5. 犯罪歴や債務状況を調べても問題ありませんか?
- 7.6 Q6. 採用調査を外部の調査会社に依頼してもよいですか?
- 7.7 Q7. 採用調査で集めた情報はどのように管理すべきですか?
- 7.8 Q8. 採用調査でどこまで調べてよいのか分かりません。
- 7.9 Q9. 採用調査を行わなかった場合、企業にリスクはありますか?
- 7.10 Q10. 採用調査の法的根拠やガイドラインはどこで確認できますか?
- 7.11 採用調査の費用はどのくらいかかるのか?
- 7.12 採用調査はどのようにして行われるのか?
- 8 まとめ:採用調査の費用と法律の真実
採用調査の基本と目的
採用調査は、企業が求職者の経歴や適性を確認し、適切な人材を選定するための重要なプロセスです。これにより、履歴書や面接だけでは把握しきれない情報を得ることができ、採用後のミスマッチやトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
企業は採用の自由を有しており、求職者の情報を調査すること自体は合法とされています。しかし、調査方法や内容には法律上の制約があり、プライバシーの侵害や差別的な取り扱いを避ける必要があります。例えば、厚生労働省は本籍や家族構成、宗教など、採用選考時に配慮すべき事項を示しており、これらの情報を不適切に扱うことは問題となります。
具体的には、求職者の同意を得ずに個人情報を収集したり、職務と無関係な私生活の情報を調査することは、プライバシー権の侵害として違法と判断される可能性があります。そのため、企業は採用調査を行う際には、法令を遵守し、適切な範囲と方法で情報を収集することが求められます。
採用調査の目的と意義
採用調査の主な目的は、候補者の経歴や適性を事前に確認し、企業と候補者のミスマッチを防ぐことです。これにより、入社後のトラブルや早期退職のリスクを低減し、組織の安定性を保つことができます。
具体的には、候補者の学歴や職歴、過去の勤務態度、犯罪歴の有無などを調査します。これらの情報を把握することで、企業は候補者が自社の文化や業務内容に適しているかを判断しやすくなります。
また、採用調査は企業のコンプライアンス強化にも寄与します。不適切な人材の採用を未然に防ぐことで、企業の社会的信用を維持し、法的リスクを回避することが可能です。
さらに、採用調査を通じて候補者の強みや特性を理解することで、入社後の適切な配置や育成計画の策定にも役立ちます。これにより、従業員のモチベーション向上や生産性の向上が期待できます。
要するに、採用調査は企業が適切な人材を確保し、組織の健全な発展を支えるための重要な手段と言えるでしょう。
採用調査は法律的に問題ないのか
採用調査を行うこと自体は法律で禁止されていませんが、その方法や内容によっては違法となる可能性があります。企業には「採用の自由」が認められており、応募者の適性や能力を評価するために必要な情報を収集することが許されています。しかし、個人情報保護法や労働基準法などの関連法令により、収集できる情報やその方法には制限が設けられています。
例えば、応募者の人種、信条、社会的身分、宗教、支持政党、労働組合への加入状況、医療情報など、差別の原因となる可能性がある事項の調査は法律で禁止されています。また、応募者の同意を得ずに個人情報を収集・利用することも違法になる可能性があるとされてます。
さらに、採用調査の方法にも注意が必要です。不正な手段で情報を入手したり、プライバシーを侵害するような調査を行った場合、企業は不法行為として損害賠償責任を問われる可能性があります。そのため、採用調査を実施する際は、応募者の同意を得た上で、職務遂行能力と合理的に関連性のある事項に限定し、適切な方法で行うことが求められます。
要するに、採用調査は法律的に問題ない範囲で適切に行うことが可能ですが、個人情報保護やプライバシーの尊重、差別の禁止など、関連法令を遵守することが不可欠です。
\採用調査ならPIO探偵事務所にお任せください/
採用調査と関連用語の違い
採用調査は、企業が新たな人材を採用する際に候補者の経歴や背景を確認するプロセスです。これにより、企業は候補者の適性や信頼性を評価し、採用後のリスクを最小限に抑えることができます。
この採用調査と混同されやすい用語として、「バックグラウンドチェック」「リファレンスチェック」「身辺調査」があります。これらはそれぞれ異なる目的や方法で行われるため、正確な理解が求められます。
以下で詳しく解説していきます。
バックグラウンドチェックとの違い
採用調査とバックグラウンドチェックは、どちらも候補者の経歴や適性を確認する手法ですが、目的や方法に違いがあります。
採用調査は、企業が新たな人材を採用する際に、候補者のスキルや経験が自社のニーズに合致しているかを判断するためのプロセスです。これには、候補者の職歴や学歴、適性などを総合的に評価することが含まれます。
一方、バックグラウンドチェックは、候補者の過去の経歴や犯罪歴、信用情報などを確認するプロセスで、主に候補者の信頼性やリスクを評価することを目的としています。具体的には、学歴や職歴の確認、犯罪歴の有無、反社会的勢力との関係の有無などが調査対象となります。
これらの違いを理解することで、企業は採用プロセスにおいて適切な手法を選択し、より効果的な人材選びが可能となります。
リファレンスチェックとの違い
リファレンスチェックは、採用候補者の前職や現職の上司、同僚、部下などから、業務遂行能力や人柄、職場での行動などについて情報を収集する手法です。これにより、候補者の強みや弱み、職場での適応性など、面接や書類選考だけでは把握しきれない側面を明らかにできます。
一方、バックグラウンドチェックは、候補者が提供した情報の正確性や、企業にとってリスクとなり得る要素の有無を確認するための調査です。具体的には、学歴や職歴の詐称、犯罪歴、反社会的勢力との関係、債務状況などが対象となります。
両者の主な違いは、リファレンスチェックが候補者の業務能力や人柄などのポジティブな情報を第三者から得ることを目的とするのに対し、バックグラウンドチェックは候補者の提供情報の正確性や潜在的なリスクを確認することに重点を置いている点です。
日本では、個人情報保護法の施行以降、バックグラウンドチェックの実施が慎重になりつつありますが、リファレンスチェックは候補者の同意を得た上で行われるため、コンプライアンスを遵守しやすい手法として注目されています。
身辺調査との違い
採用調査と身辺調査は、目的と範囲において明確な違いがあります。採用調査は、企業が新たな人材を採用する際に、候補者の学歴や職歴、資格、スキルなど、業務遂行に直接関連する情報を確認するプロセスです。これにより、候補者が企業の求める要件を満たしているかを判断し、採用のミスマッチを防ぐことが目的となります。
一方、身辺調査は、特定の個人の経歴や背景、交友関係、生活環境など、より広範な情報を調査するものです。この調査は、結婚や取引など、採用以外の目的でも行われることがあり、個人のプライベートな側面まで踏み込むことが特徴です。
採用調査は、業務に関連する情報の確認に重点を置き、候補者の適性や能力を評価するために行われます。これに対し、身辺調査は、個人の私生活や人間関係など、業務とは直接関係のない領域まで調査対象とする点で異なります。
企業が採用時に身辺調査を行う場合、個人情報保護法や職業安定法などの法的規制に注意が必要です。特に、候補者の同意なしにプライバシーに関わる情報を収集することは、法的リスクを伴う可能性があります。そのため、採用調査を実施する際は、業務に直接関連する情報のみに焦点を当て、出来る限り候補者の同意を得た上で適切に行うことが求められます。
要するに、採用調査は業務関連の情報確認に特化し、身辺調査は個人の私生活や背景まで広範に調査するものであり、目的と範囲において明確な違いがあります。
採用調査で確認する項目

採用調査は、候補者の経歴や人物面を多角的に確認し、採用後のミスマッチやトラブルを防ぐために実施されます。企業が安心して雇用判断を行うためには、適正かつ公正な採用調査を行うことが重要です。
以下では、採用調査で一般的に確認される主な項目を紹介します。
学歴と職歴の確認
採用調査における学歴と職歴の確認は、応募者の信頼性を確保し、企業のリスクを最小限に抑えるために不可欠です。近年、経歴詐称の事例が増加しており、特に学歴や職歴の偽装が問題視されています。
学歴の確認方法
1. 卒業証明書の提出依頼: 応募者に対し、最終学歴の卒業証明書や成績証明書の提出を求めます。これにより、履歴書の記載内容と実際の学歴が一致しているかを確認できます。
2. 教育機関への直接確認: 応募者の同意を得た上で、卒業した教育機関に直接問い合わせを行い、在籍期間や卒業の有無を確認します。ただし、個人情報保護の観点から、教育機関が情報提供を拒否する場合もあります。
職歴の確認方法
1. 在籍証明書や退職証明書の提出依頼: 応募者に前職の在籍証明書や退職証明書の提出を求め、在籍期間や職務内容を確認します。これにより、履歴書の職歴と実際の勤務状況が一致しているかを確認できます。
2. リファレンスチェックの実施: 応募者の同意を得た上で、前職の上司や同僚に連絡を取り、勤務態度や業務遂行能力についての評価を収集します。これにより、書類や面接だけでは把握しきれない情報を得ることができます。
注意点
– 個人情報保護の遵守: 学歴や職歴の確認を行う際は、応募者の同意を得ることが必須です。無断での調査は個人情報保護法に抵触する可能性があります。
– 情報の正確性の確保: 提出された証明書類が偽造されている可能性も考慮し、必要に応じて教育機関や前職への直接確認を行うことが重要です。
これらの手法を適切に組み合わせることで、応募者の学歴や職歴の正確性を確認し、企業の採用リスクを低減することが可能となります。
勤怠状況やトラブル履歴
採用調査において、候補者の前職での勤怠状況やトラブル履歴を確認することは、企業にとって非常に重要です。これにより、候補者の勤務態度や職場での適応能力を把握し、採用後のリスクを最小限に抑えることができます。
具体的には、以下の点を調査します:
– 勤怠状況の確認:前職での出勤率や遅刻・早退の頻度を調べ、規則正しい勤務ができていたかを確認します。
– トラブル履歴の確認:過去に職場で問題行動や人間関係のトラブルがなかったかを調査し、職場環境への適応力を評価します。
これらの情報は、前職の上司や同僚からのフィードバックを通じて得られることが多いです。例えば、前職での勤務態度やチームワーク、信頼性についての評価を収集します。
このような調査を行うことで、企業は候補者が自社の文化や業務に適しているかを総合的に判断し、採用後のミスマッチや早期退職のリスクを軽減できます。
反社会的勢力との関係チェック
採用調査における反社会的勢力との関係チェックは、企業の信頼性と安全性を守るために不可欠です。政府は2007年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表し、企業に対し、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを求めています。
具体的なチェック方法として、以下の手段が挙げられます。
– インターネット検索:候補者の名前を検索エンジンで調べ、過去のニュース記事やSNSの投稿から反社会的勢力との関係がないかを確認します。
– 反社チェックツールの活用:専門のデータベースを利用し、候補者が反社会的勢力と関係していないかを調査します。
– 調査会社への依頼:専門の調査会社に依頼し、より詳細なバックグラウンドチェックを行います。
これらの方法を組み合わせることで、より精度の高いチェックが可能となります。ただし、個人情報保護法やプライバシーの観点から、調査は適切な範囲内で行い、候補者の同意を得ることが重要です。
反社会的勢力との関係を持つ従業員を採用してしまうと、企業の信用失墜や法的リスクが生じる可能性があります。そのため、採用時の反社チェックは、企業防衛の観点からも欠かせないプロセスと言えるでしょう。
犯罪歴や債務状況の確認
採用調査において、候補者の犯罪歴や債務状況の確認は、企業のリスク管理上重要な項目です。しかし、日本ではこれらの情報の取得には法的な制約があり、慎重な対応が求められます。
犯罪歴の確認方法
日本では、警察が保有する犯罪歴のデータベースは原則非公開であり、第三者が直接照会することはできません。そのため、以下の方法で間接的に確認を行います。
– メディアチェック:新聞やニュースなどの公開情報を検索し、候補者が過去に報道された事件に関与していないかを調査します。
– 独自データベースの活用:探偵社や調査会社が独自に構築したデータベースを用いて、過去の事件や訴訟記録を確認します。
債務状況の確認方法
候補者の債務状況や破産歴の確認も、直接的な情報取得が難しいため、以下の方法が用いられます。
– 官報の確認:官報に掲載された破産情報を調査し、候補者が過去に自己破産をしていないかを確認します。
– 信用情報機関の利用:候補者の同意を得た上で、信用情報機関から債務状況を照会することが可能です。ただし、個人情報保護法に基づき、適切な手続きを踏む必要があります。
注意点
これらの調査を行う際は、以下の点に注意が必要です。
– 本人の同意取得:個人情報保護法により、候補者の同意なしに個人情報を取得することは違法となる可能性があります。調査前に必ず同意を得ることが重要です。
– 調査範囲の限定:業務遂行に必要な範囲内での情報収集に留め、不必要なプライバシー侵害を避けることが求められます。
– 専門機関の活用:法的リスクを回避するため、専門の調査会社や探偵社に依頼することが望ましいです。これにより、適切な手法での調査が可能となります。
採用調査における犯罪歴や債務状況の確認は、企業の安全性を確保するために重要ですが、法的な制約を遵守し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
\採用調査ならPIO探偵事務所にお任せください/
採用調査の進め方
採用調査を適切に進めるためには、以下のステップが重要です。
まず、採用予定者から調査の同意を得ることが必要です。これは、個人情報保護法に基づき、調査対象者の同意なしに個人情報を収集・利用することが禁止されているためです。同意を得る際には、調査の目的や範囲を明確に説明し、書面での同意を取得することが望ましいでしょう。
次に、調査会社への依頼方法を検討します。自社で調査を行うことも可能ですが、専門的な知識やリソースが必要となるため、多くの企業は専門の調査会社に依頼しています。調査会社を選定する際には、調査内容や費用、実績などを比較検討し、自社のニーズに合った業者を選ぶことが重要です。
最後に、調査の実施と結果の受け取りです。調査会社が採用予定者の経歴や職歴、勤怠状況、反社会的勢力との関係などを確認し、報告書としてまとめます。企業はこの報告書をもとに、採用の最終判断を行います。調査結果は慎重に取り扱い、採用選考の公正性を保つよう努めましょう。
採用予定者からの同意取得
採用調査を実施する際、採用予定者からの同意取得は法的に必須です。個人情報保護法では、個人情報の収集・利用には本人の同意が必要と定められています。同意を得ずに調査を行うと、違法行為とみなされ、企業の信用失墜や法的責任を問われる可能性があります。
同意取得の際は、以下のポイントを押さえることが重要です。
– 調査の目的と範囲を明確に伝える:採用調査の目的や具体的な調査項目を採用予定者に説明し、理解を得ることが求められます。
– 書面での同意を得る:口頭での同意も可能ですが、後のトラブルを防ぐため、書面で同意を取得することが望ましいです。
– 同意の自由意志を尊重する:採用予定者が自由な意思で同意できる環境を整え、強制や圧力をかけないよう注意が必要です。
これらの手順を踏むことで、採用調査を適法かつ円滑に進めることができます。
採用調査を専門の調査会社に依頼する際の手順
採用調査を外部の専門調査会社に依頼する場合は、適法性と信頼性を確保するために、以下の手順を踏むことが重要です。
1. 信頼できる調査会社の選定
まず、採用調査の実績が豊富で、法令を遵守して業務を行う信頼性の高い調査会社を選定します。過去の採用調査事例や顧客からの評価、コンプライアンス体制などを確認し、安心して依頼できる業者を見極めましょう。
2. 調査目的と範囲の明確化
次に、採用調査の目的と調査範囲を明確にします。たとえば、経歴の確認、職務適性、反社会的勢力との関係の有無など、調査内容を具体的に設定することで、調査会社は適切な手法を選択し、効率的に採用調査を進められます。
3. 調査期間と予算の設定
採用調査にかける期間と予算を事前に設定し、調査会社と共有します。スケジュールや費用を明確にすることで、調査の進行が円滑になり、予算超過や納期遅延を防ぐことができます。
4. 調査対象者からの同意取得
採用調査を行う前には、必ず対象者本人から書面による同意を得る必要があります。無断での調査は法的リスクを伴うため、個人情報保護法などの関連法令を遵守し、透明性の高い手続きを行いましょう。
5. 調査会社への正式な依頼
準備が整ったら、採用調査の正式な依頼を行います。契約書には、調査目的・調査方法・報告書の形式・守秘義務などを明記し、依頼者と調査会社の認識を一致させておくことが大切です。
6. 調査の進行と結果の受け取り
採用調査の進行中は、定期的に進捗を確認し、必要に応じて調査内容の調整を行います。調査完了後には、報告書を受け取り、内容の正確性と客観性を確認したうえで、採用判断の参考資料として活用します。
これらの手順を踏むことで、採用調査を効果的かつ適法に実施し、採用リスクを最小限に抑えながら、公正で透明性の高い採用活動を行うことができます。
調査の実施と結果の受け取り
採用調査の実施と結果の受け取りは、企業が適切な人材を確保するために重要なプロセスです。まず、調査会社と詳細な打ち合わせを行い、調査の目的や範囲、具体的な項目を明確に設定します。これにより、調査の方向性が定まり、必要な情報を的確に収集できます。
次に、調査会社が候補者の学歴や職歴、勤怠状況、反社会的勢力との関係、犯罪歴、債務状況など、多岐にわたる項目を調査します。これらの情報は、候補者の適性や信頼性を判断する上で欠かせません。
調査が完了すると、調査会社から詳細な報告書が提供されます。この報告書には、各項目の調査結果が記載されており、企業はこれを基に候補者の総合的な評価を行います。報告書の内容を慎重に精査し、採用の可否や配置先の決定に役立てることが求められます。
また、調査結果を受け取った後、候補者に対して適切なフィードバックを行うことも重要です。調査で得られた情報を踏まえ、候補者の強みや改善点を伝えることで、双方の信頼関係を築くことができます。
このように、採用調査の実施から結果の受け取り、そしてその活用までの一連の流れを適切に管理することで、企業はより適切な人材を確保し、組織の発展に寄与することが可能となります。
採用調査の費用について

採用調査の費用は、調査内容や対象者の役職、調査機関によって大きく異なります。一般的な採用調査では、1人あたり3万~5万円程度が相場とされています。
この費用の差は、調査の深度や範囲、対象者の重要度によって生じます。例えば、一般的なポジションの候補者に対する基本的な経歴や素行の確認であれば、比較的低コストで済みます。一方、役員候補や重要なポストを担う人材に対しては、より詳細で綿密な調査が求められ、その分費用も高くなります。
具体的には、ある調査会社では、一般的な採用調査(経歴、性格素行、健康、勤怠、退職理由、生活状況の確認)を中2日で48,000円で提供しています。また、重要ポストや役職者向けの特別な調査では、調査期間が中4日で63,000円から100,000円と設定されています。
採用調査を検討する際は、調査の目的や必要な情報の範囲を明確にし、複数の調査会社から見積もりを取ることで、適切な費用で効果的な調査を実施することが可能です。
海外と日本における採用調査の違い
採用調査の手法や目的は、国や地域によって大きく異なります。日本と海外では、企業文化や法制度の違いから、採用調査の進め方や重視するポイントに差が生じています。
日本では、新卒一括採用や終身雇用といった独自の雇用慣行が根付いており、採用時には候補者の人間性や企業文化への適応性が重視される傾向があります。一方、海外、特に欧米諸国では、通年採用が一般的であり、即戦力となるスキルや経験が評価の中心となっています。
例えば、アメリカでは職務経歴や専門的なスキルが採用の決定要因となることが多く、候補者の過去の実績や具体的な能力が詳細に評価されます。これに対し、日本では長期的な視点での人材育成を前提とし、ポテンシャルや組織への適応力が重視されるケースが多いです。
以下で詳しく解説していきます。
アメリカの採用調査事情
アメリカでは、採用時に候補者の経歴や背景を確認する「バックグラウンドチェック(Background Check)」が広く行われています。これは、企業が適切な人材を確保し、トラブルや法的リスクを防止するための重要なプロセスとされています。
バックグラウンドチェックの内容は、職種や業界、州の法律によって異なりますが、一般的には学歴・職歴の確認、犯罪歴の有無、職務上の資格、クレジット(信用)情報などが含まれます。特に金融業界や管理職など、責任の重いポジションでは財務状況の確認が行われることもあります。また、一部の企業ではSNS(ソーシャルメディア)上の公的な投稿内容を確認するケースもありますが、これは標準的な手法ではなく、慎重な取り扱いが求められます。
こうした調査を実施する主な目的の一つに、企業が「ネグリジェント・ハイヤリング(過失採用)」と見なされるリスクを避けることがあります。つまり、企業が合理的な確認を怠った結果として不適切な人材を採用し、その人物が職務中に問題を起こした場合、雇用主が法的責任を問われる可能性があるのです。
ただし、採用調査を行う際には候補者のプライバシー保護と法令遵守が極めて重要です。アメリカでは「公正信用報告法(FCRA)」に基づき、候補者の同意を得ずに第三者から情報を取得することは禁止されています。また、調査結果の利用にあたっては、「雇用差別禁止法(EEOCガイドライン)」などに従い、性別・人種・宗教・年齢など、職務能力と無関係な要素を採用判断に用いることは違法とされています。
このように、アメリカの採用調査は、企業が信頼性と法令遵守を両立させながら、リスクを最小限に抑え、適切な人材を採用するために欠かせないプロセスとなっています。
日本での採用調査に伴うリスク
日本における採用調査は、企業が適切な人材を確保するための有効な手段ですが、その実施方法によっては法的リスクや倫理的な問題が生じる可能性があります。特に、候補者の同意を得ずに前職への照会や個人情報の収集を行うことは、個人情報保護法や職業安定法などに抵触するおそれがあります。たとえば、前職の勤務状況や退職理由を本人の同意なしに確認する行為は、プライバシーの侵害と見なされる場合があります。
また、採用調査で得られた情報を不適切に利用した場合、差別的な採用と判断されるリスクもあります。候補者の思想・信条、宗教、労働組合への加入状況、家族構成など、職務適性と直接関係のない情報を調査・選考に用いることは、厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」や職業安定法の趣旨に反します。
さらに、自社で採用調査を行う場合、情報の正確性や調査手法の適法性を確保することが難しく、結果として個人情報の不適切な取扱いや虚偽情報の利用など、企業側の法的リスクが高まるおそれがあります。そのため、調査を行う際は、候補者の明確な同意を得ること、収集範囲を採用目的に必要な最小限に限定すること、法令を遵守した調査手法を用いることが重要です。
これらの点を遵守することで、企業はプライバシー保護と法令遵守を両立させながら、採用リスクを最小限に抑え、適切な人材の確保につなげることができます。
採用調査に関するよくある質問
Q1. 採用調査とは何ですか?
採用調査とは、企業が採用候補者の経歴・職務実績・人物面などを確認し、採用判断に必要な情報を得るための調査です。具体的には、学歴・職歴・資格の確認、前職照会(リファレンスチェック)、犯罪歴の有無の確認などが含まれる場合があります。ただし、日本では調査の方法や範囲に法的な制約があり、慎重に実施する必要があります。
Q2. 採用調査を行う際に候補者の同意は必要ですか?
はい、必要です。候補者の個人情報を取得・利用する場合は、個人情報保護法に基づき、利用目的を明示し、本人の同意を得ることが原則です。特に前職調査や第三者から情報を取得する場合、同意なしに実施すると違法となるおそれがあります。
Q3. 前職の勤務態度や退職理由を確認しても良いですか?
本人の同意を得た場合に限り、確認することが可能です。ただし、必要最小限の範囲で行い、得られた情報は採用判断以外の目的に利用してはいけません。本人の同意がない状態で前職に照会することは、プライバシー侵害や個人情報保護法違反となるリスクがあります。
Q4. SNS(ソーシャルメディア)の投稿内容を採用調査に利用しても良いですか?
公開されている情報であっても、候補者の思想・信条・人種・性別・宗教などの属性情報を採用判断に使うことは、差別的取扱いとして問題になります。SNSの内容を調査に利用する場合は、職務適性に直接関係する情報のみに限定し、差別や偏見につながらないよう注意が必要です。
Q5. 犯罪歴や債務状況を調べても問題ありませんか?
犯罪歴や債務状況の調査は、本人の同意を得たうえで、合法的な範囲で行うことが前提です。これらは非常に慎重な取扱いが求められる情報のため、違法な手段はもちろん避ける必要があります。信頼できる探偵事務所であれば、「探偵業法」に基づき、適法かつ公正な方法で調査を行うことが可能です。採用調査として実施する際は、目的を明確にし、必要最小限の範囲にとどめることが重要です。
Q6. 採用調査を外部の調査会社に依頼してもよいですか?
可能ですが、委託先の調査会社が適法な手法で調査を行っているかを確認する必要があります。依頼する際は、委託契約書に個人情報の取扱い方法、調査範囲、報告内容、守秘義務などを明記し、委託元にも管理責任があることを理解しておくことが重要です。
Q7. 採用調査で集めた情報はどのように管理すべきですか?
採用調査で得た情報は、利用目的の範囲内でのみ使用し、採用選考終了後は速やかに廃棄または削除することが推奨されます。また、個人情報保護法に基づき、適切な安全管理措置(アクセス制限、保管ルール、漏えい防止策など)を講じる必要があります。
Q8. 採用調査でどこまで調べてよいのか分かりません。
基本原則として、調査は「職務遂行に必要な範囲」に限定することが求められます。厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、出身地・家族構成・思想信条・宗教・支持政党など、職務に無関係な事項の収集・質問は行わないよう定められています。
Q9. 採用調査を行わなかった場合、企業にリスクはありますか?
日本では「採用調査を行わなかったこと」による直接的な法的責任は基本的にありません。ただし、経歴詐称や不正行為の見落としなどで後にトラブルが発生した場合、採用時の確認不足による損害リスクが生じることがあります。そのため、法令に沿った適正な調査を行うことが望ましいです。
Q10. 採用調査の法的根拠やガイドラインはどこで確認できますか?
採用調査には、個人情報の取扱いや公正な採用に関する法令が関係します。主な根拠は次のとおりです。
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
👉 個人情報保護委員会 / 法令全文(e-Gov) - 職業安定法 第5条の4(公正な採用選考)
👉 職業安定法(e-Gov) - 厚生労働省「公正な採用選考の基本」指針
👉 厚生労働省公式ページ - 労働基準法・男女雇用機会均等法(差別的取扱いの禁止)
👉 厚生労働省案内
\採用調査ならPIO探偵事務所にお任せください/
採用調査の費用はどのくらいかかるのか?
採用調査の費用は、調査内容や対象者の役職、調査の深度によって大きく変動します。一般的な採用調査では、1人あたり3万~5万円程度が相場とされています。この範囲内で、経歴や性格、健康状態、勤怠状況、退職理由、生活状況などの基本的な項目が調査されます。
一方、役職者や重要なポストを担う候補者に対する詳細な調査では、1人あたり5万~15万円程度の費用がかかることもあります。この場合、調査内容はより綿密で、経歴の詳細な検証や、過去の業績、対人関係、リーダーシップ能力など、多岐にわたる項目が含まれます。
また、調査期間は通常約1週間程度とされていますが、調査の深度や対象者の数によっては、これより長くなる場合もあります。費用と期間は、調査の目的や必要性に応じて適切に設定することが重要です。
採用調査を検討する際は、調査会社と具体的なニーズを共有し、見積もりを取ることで、最適なプランを選択することが望ましいでしょう。
採用調査はどのようにして行われるのか?
採用調査は、企業が応募者の適性や信頼性を確認するために行う重要なプロセスです。具体的には、以下の手順で進められます。
1. 応募者からの同意取得
まず、個人情報保護の観点から、応募者に対して調査の目的や範囲を明確に説明し、書面で同意を得ることが必要です。これにより、プライバシーの侵害を防ぎ、信頼関係を築くことができます。
2. 調査項目の選定
次に、調査する項目を決定します。一般的には、学歴や職歴、資格、犯罪歴、債務状況などが含まれます。ただし、厚生労働省の指針により、本籍地や家族構成、思想・信条など、採用に直接関係のない情報の収集は避けるべきとされています。
3. 調査方法の選択
調査は、以下の方法で行われます。
– 書類確認:応募者が提出した履歴書や職務経歴書、資格証明書などの書類を精査します。
– リファレンスチェック:前職の上司や同僚に連絡を取り、勤務態度や業務遂行能力についての評価を確認します。
– 公的記録の確認:犯罪歴や債務状況など、公的なデータベースを利用して情報を取得します。
4. 調査結果の分析と活用
収集した情報を分析し、応募者の適性やリスクを評価します。その結果を基に、採用の可否や配置先の決定を行います。
注意点
採用調査を行う際は、個人情報保護法や職業安定法などの関連法規を遵守し、必要最小限の情報収集にとどめることが重要です。違法な調査を行うと、企業の信頼性が損なわれるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
以上の手順を適切に実施することで、企業は応募者の適性を正確に把握し、適切な人材を採用することが可能となります。
まとめ:採用調査の費用と法律の真実
今回は、採用調査に関心を持つ方に向けて、
– 採用調査の基本と目的
– 採用調査で確認する項目
– 採用調査の進め方
– 採用調査の費用について
上記について、解説してきました。
採用調査は企業にとって重要なプロセスですが、その費用や法律面での理解が不十分な場合、思わぬ問題に直面することがあります。この記事では、採用調査を行う際に知っておくべき費用の内訳や関連する法律について詳しく説明しました。これにより、あなたが抱える不安や疑問を少しでも解消できたのではないでしょうか。
これまでの内容を踏まえて、採用調査をスムーズに進めるために、まずは法律の基本を理解し、必要な費用をしっかりと把握することをお勧めします。これにより、より安心して調査を進めることができるでしょう。
あなたが今までに培ってきた経験や努力は、必ずしも無駄にはなりません。むしろ、それらは今後の成功に向けた大きな力となります。
未来に向けて、採用調査があなたのビジネスにとって有益なものとなることを期待しています。前向きな気持ちで取り組んでいきましょう。
具体的な行動として、まずは法律に詳しい専門家に相談することをお勧めします。あなたの成功を心から応援しています。

PIO探偵事務所編集部監修
本記事はPIO探偵事務所の編集部が企画・編集・監修を行いました。