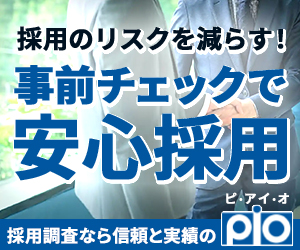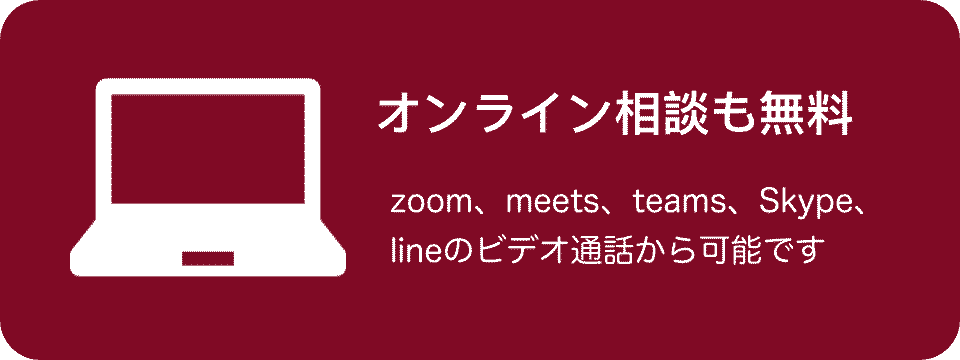バックグラウンドチェックの実施方法と費用を徹底検証【保存版】

「採用候補者の経歴に嘘はないか、しっかり見極めたいけど、どう調査すればいいのだろう…」
「バックグラウンドチェックを実施したいけど、費用や法律的な問題が心配…」
採用担当者であれば、このような不安を感じる場面もあるでしょう。
採用後のミスマッチや思わぬトラブルを防ぐためにも、正しい知識を持って調査を進めることが大切です。
この記事では、採用候補者の経歴を正確に把握し、安心して採用活動を進めたい方に向けて、
– バックグラウンドチェックとは何か
– バックグラウンドチェックの実施方法
– バックグラウンドチェックの注意点
– バックグラウンドチェックのよくある質問
上記について、解説しています。
初めて調査を行う際は、分からないことばかりで戸惑うかもしれません。
この記事を読めば、調査の全体像から具体的な費用まで理解でき、安心して手続きを進められるようになります。
ぜひ参考にしてください。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴53年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。
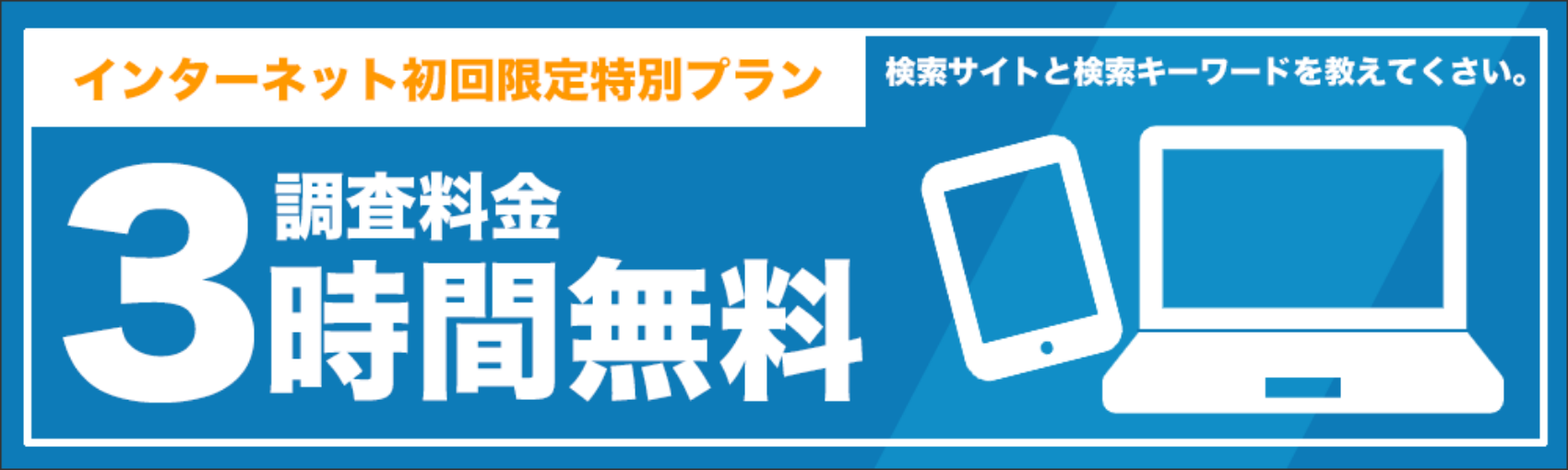
目次
バックグラウンドチェックとは何か
バックグラウンドチェックとは、採用候補者の経歴や申告内容に嘘がないかを確認するための身元調査のことです。
採用におけるミスマッチを防ぎ、企業の信頼性を守るために、多くの企業で導入が進んでいる重要なプロセスと言えるでしょう。
この調査は、候補者本人の同意を得た上で、専門の調査会社を通じて客観的な事実を確認する形で行われます。
なぜなら、履歴書や面接だけでは候補者のすべてを把握することが難しいためです。
もし経歴を偽っていたり、何らかのリスクを抱えた人材を採用してしまったりすると、後々大きなトラブルに発展しかねません。
入社後の業績不振や、他の従業員への悪影響、最悪の場合には企業のブランドイメージを損なう事態を防ぐことが、この調査の大きな目的です。
具体的には、学歴や職歴の詐称がないかの確認、反社会的勢力との関わりの有無、過去の犯罪歴などを調査します。
他にも、インターネットやSNSでの投稿内容をチェックし、候補者のコンプライアンス意識や人物像を多角的に把握することも珍しくありません。
これらの調査を通じて、企業は安心して採用活動を進めることができるようになります。
バックグラウンドチェックの基本概念
バックグラウンドチェックとは、主に企業の採用選考において、候補者の経歴や申告内容に虚偽がないかを確認するために実施される調査のことです。単に履歴書や職務経歴書に記載された学歴や職歴の真偽を確かめるだけでなく、候補者の信頼性を多角的に評価する目的があります。
この調査を通じて、企業は経歴詐称による採用のミスマッチを未然に防ぎ、組織全体の健全性を保つことが可能になるでしょう。また、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力との関わりや、業務に重大な影響を及ぼす可能性のある犯罪歴などを事前に把握することも重要な役割の一つです。
調査の実施にあたっては、個人情報保護の観点から必ず候補者本人からの同意を得ることが法律で定められており、企業の信頼性を担保する上でも不可欠な手続きといえます。
なぜバックグラウンドチェックが必要か
企業がバックグラウンドチェックを行う主な目的は、採用候補者の経歴や申告内容に虚偽がないかを確認し、採用における潜在的なリスクを回避することにあります。
履歴書や面接だけでは、候補者の能力や人柄を正確に見抜くことは難しく、経歴詐称や不都合な事実を隠している可能性も否定できません。過去の経歴詐称が発覚すれば、企業の信用失墜や業績悪化につながる恐れがあるでしょう。
また、反社会的勢力との関わりや過去の犯罪歴などを事前に把握することは、コンプライアンス遵守や他の従業員の安全確保の観点から極めて重要です。採用後のミスマッチによる早期離職は、企業にとって大きな損失となるため、候補者の適性を客観的に判断する手段としても活用されています。これらのリスクを事前に排除し、健全な組織運営を維持するために、バックグラウンドチェックの必要性が高まっているのです。
バックグラウンドチェックの主な種類
バックグラウンドチェックには、実はいくつかの種類があり、調査したい内容や採用ポジションに応じて使い分けることが大切です。
すべての候補者に同じ調査を行うのではなく、目的に合わせて最適な手法を選択することが、採用のミスマッチを防ぐための重要な第一歩になるでしょう。
なぜなら、役職や職務内容によって、企業が確認すべきリスクは大きく異なるからです。
例えば、会社の経営に関わる役員候補者と、お客様と直接関わる営業職とでは、求められる資質や経歴の重要性が異なります。
それぞれのポジションに合わせた調査を行わなければ、本当に必要な情報を得られない可能性があるのです。
具体的には、候補者の実績や人柄について前職の上司や同僚にヒアリングする「リファレンスチェック」や、学歴・職歴の詐称がないかを確認する調査など、その手法は多岐にわたります。
以下で、それぞれのチェック方法の特徴や、どのような場合に有効なのかを詳しく解説していきましょう。
信用情報の確認
バックグラウンドチェックにおける「信用情報の確認」とは、候補者の経済的な信用状況や金銭管理に関するリスクを把握するための調査を指します。
特に金融機関や経理・財務部門など、金銭を直接取り扱う職種では、横領・着服といった不正防止の観点から重視される傾向にあります。
ただし、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(日本信用情報機構)などの信用情報機関に、企業が採用目的で照会することはできません。
これらの機関の情報は、加盟する金融業者などが「与信取引」に限って利用できる仕組みのため、採用選考目的の利用は禁止されています。
そのため、信用状況の確認を行う場合は、候補者本人の同意を得たうえで、本人が自身の信用情報を開示し、その内容を企業に提出してもらう方法が一般的です。
このように「本人開示による提出」であれば、個人情報保護法上も問題ありません。
なお、本人の同意なく信用情報を収集・利用する行為は、個人情報保護法や信用情報機関の規約に違反する可能性があります。
経済的信用に関する調査は、本人のプライバシー保護と法令遵守を最優先に進めることが重要です。
犯罪歴の確認
採用候補者の犯罪歴の有無を確認することは、企業にとってコンプライアンス遵守やリスク管理の観点から重要な取り組みの一つです。
特に金融・運輸・医療・教育・警備など、社会的責任が重い職種では、過去の不正行為や法令違反の有無を確認することが、企業の信頼維持に直結します。
ただし、日本では警察や法務省などの捜査・司法機関以外が、個人の犯罪歴を網羅的に照会することはできません。
民間企業や調査会社がアクセスできる公的な「犯罪歴データベース」は存在せず、照会を行うと違法行為となる可能性があります。
そのため、企業が採用時に確認できる範囲は、あくまで公開情報や本人が提供した資料に限られます。
具体的には、過去の新聞・報道記事、官報、裁判所の公開記録、インターネット上の法的公告などを調査するケースが一般的です。
また、調査会社に依頼する場合も、これら公開情報を独自に整理したデータベースを用いて確認する方法に限られます。
本人の同意を得ずに犯罪歴を調査することは、個人情報保護法上の「要配慮個人情報の不正取得」に該当するおそれがあります。
特に「逮捕歴」「前科」などの情報は極めてセンシティブであり、本人の名誉や社会的信用を損なう可能性があるため、慎重な取扱いが求められます。
一方で、反社会的勢力との関係を確認する反社チェックや、運転記録証明書の取得によって重大な交通違反歴を確認するなど、合法的なリスク管理手段は存在します。
これらは本人同意のうえで行う限り、法的にも問題ありません。
学歴と職歴の確認
採用選考において、候補者が提出した履歴書や職務経歴書に記載された学歴や職歴に偽りがないかを確認する作業は、採用後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。
学歴の確認は、卒業したとされる大学などから卒業証明書を取り寄せてもらい、提出を求める方法が最も一般的でしょう。これは公的な書類のため信頼性が高いといえます。
より厳密な調査が必要な場合は、本人の同意を得た上で学校に直接問い合わせることもありますが、個人情報保護の観点から回答を得られないケースも少なくありません。
一方、職歴の確認では、以前の勤務先に在籍していた事実や期間、役職などを確かめます。前職の上司や同僚に候補者の勤務態度などをヒアリングするリファレンスチェックが有効な手段となりますが、この調査も必ず本人の同意を得てから実施する必要があります。
これらの確認を通じて、企業は候補者の信頼性を見極め、採用リスクを低減させることが可能になります。
バックグラウンドチェックの実施方法
バックグラウンドチェックを実施する方法は、大きく分けて「自社で直接行う方法」と「専門の調査会社へ依頼する方法」の2つに分類されます。
採用候補者の経歴を正確に把握するためには、自社の状況や調査したい内容に応じて、最適な方法を選択することが非常に重要でしょう。
なぜなら、自社で行う方法は費用を安く抑えられるという大きな利点がありますが、得られる情報が限定的になりがちで、人事担当者の負担が増えてしまう可能性があるからです。
一方で、専門の調査会社に依頼すると、法的な知識に基づいた広範で正確な調査が期待できるものの、当然ながらコストがかかるという側面も無視できません。
それぞれのメリット・デメリットを天秤にかけ、自社にとって最善の選択をすることが求められます。
では、具体的に自社で行う場合と調査会社に依頼する場合では、どのような違いがあるのでしょうか。
以下で、それぞれの実施方法の詳しい流れや特徴、注意点について、さらに掘り下げて解説していきます。
個人で行う方法
個人でバックグラウンドチェックを行うことは可能です。代表的な方法として、候補者本人の同意を得て、前職の上司や同僚に実績や勤務態度、人柄などを直接ヒアリングするリファレンスチェックが挙げられます。この方法は、費用を抑えられる点が大きな利点といえるでしょう。
また、インターネット検索を利用して過去の経歴に関するニュース記事を探したり、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSで公開されている投稿内容から発言の傾向を確認したりすることも一つの手段となります。
ただし、個人での調査は得られる情報が限定的になり、専門業者のような網羅的な確認は困難です。調査には多くの手間と時間がかかる上、個人情報保護法を遵守する必要があるため、慎重な対応が求められます。
専門業者に依頼する方法
より正確で広範囲な調査を望む場合、専門の調査会社や探偵社へ依頼する方法が一般的です。専門業者に頼むことで、個人情報保護法や探偵業法などの法律を遵守した上で、信頼性の高い情報を得られます。
依頼する際の大まかな流れは、まず複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較検討することから始まります。契約後は、調査の目的や範囲を明確に伝え、必ず調査対象者本人から調査実施に関する同意を得なければなりません。同意取得後、業者が学歴や職歴の確認、反社会的勢力との関わりなどを調査し、完了後に詳細な報告書が提出されるという手順になります。
専門業者を利用すれば、手間や時間を大幅に削減できるだけでなく、客観的で法的に問題のない調査が実現するため、多くの企業で活用されています。業者選定時には、探偵業の届出標識を確認し、実績が豊富で信頼できる会社を選ぶことが重要でしょう。
\バックグラウンドチェックならPIO探偵事務所へ/
バックグラウンドチェックの費用について
バックグラウンドチェックの費用は、調査範囲や依頼する専門機関によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えないのが実情です。
採用候補者一人当たり数万円で済む場合もあれば、重要なポジションの採用では数十万円に及ぶこともあり、費用感が分からず導入をためらう方もいるでしょう。
なぜなら、調査する項目の数やその難易度によって、必要な工数や専門性が大きく異なるからです。
基本的な経歴の確認だけでなく、反社会的勢力との関わりの有無や過去の訴訟歴、インターネット上の評判調査など、調べる範囲が広がるほど費用は高くなる傾向にあります。
採用ポジションの重要性に応じて、どこまで詳しく調べるかを決めることが、費用を考える上での第一歩です。
具体的には、学歴や職歴の確認といった基本的な調査であれば、1名あたり2万円から5万円程度が一般的な相場でしょう。
一方で、役員候補者などに対して、より踏み込んだリファレンスチェックやSNS調査、破産歴の確認などを加えると、費用は1名あたり10万円を超えるケースも少なくありません。
まずは複数の調査会社から見積もりを取り、自社のニーズに合ったプランを選択することが重要です。
個人で行う場合の費用
個人でバックグラウンドチェックを実施する場合、専門業者への依頼に比べて費用を大幅に抑えられる可能性があります。具体的な費用は、調査したい項目によって変動します。例えば、学歴を確認するために大学から卒業証明書を取り寄せる場合、発行手数料として数百円から1,000円程度がかかるでしょう。また、住民票の写しや戸籍謄本といった公的書類の取得には、1通あたり300円から450円ほどの手数料が必要です。法務局で不動産登記簿謄本などを取得する際には、1通600円程度の実費が発生します。インターネットやSNSを利用した調査は基本的に無料で行えますが、これらの実費や郵送費などを合計すると、総額で数千円から1万円を超えることも珍しくありません。調査範囲と必要な書類を事前に明確にしておくことが重要です。
専門業者に依頼する場合の費用
専門業者にバックグラウンドチェックを依頼する場合の費用は、調査する項目の範囲や深さによって大きく変動します。一般的な料金相場は、候補者1名あたり5万円から10万円程度がひとつの目安となるでしょう。
基本的な経歴の確認だけであれば数万円で済むこともありますが、反社会的勢力との関わりの有無や破産歴、訴訟歴といった詳細な調査を追加すると費用は高くなる傾向です。
多くの調査会社では、基本的な項目をまとめたパッケージプランを用意しており、自社の採用基準に合わせて必要な調査項目を追加できるオプションも提供されています。そのため、複数の業者から見積もりを取得し、調査内容と費用を比較検討することが重要になります。
依頼する際は、どこまでの情報を求めるのかを明確にしておくと、無駄なコストを抑えることができるでしょう。
バックグラウンドチェックの注意点
バックグラウンドチェックは、採用候補者の経歴を客観的に把握し、ミスマッチを防ぐ上で非常に有効な手段ですが、実施には細心の注意が求められます。
単に調査すれば良いわけではなく、法律の遵守と個人のプライバシーへの配慮を怠ると、深刻なトラブルに発展しかねないからです。
その理由は、バックグラウンドチェックが個人情報保護法や職業安定法と密接に関わっていることにあります。
候補者本人の明確な同意なしに情報を収集したり、業務遂行能力と無関係なプライベートな情報を調査したりすることは、法律に抵触する可能性があるのです。
企業のコンプライアンス意識が問われる、非常にデリケートなプロセスだと認識する必要があるでしょう。
例えば、候補者の同意を得ずに前職の同僚へ電話し、勤務態度などをヒアリングする行為は避けるべきです。
具体的には、本籍地や思想・信条、宗教といった差別につながる恐れのある情報の収集は、職業安定法で原則として禁止されています。
トラブルを未然に防ぐためにも、調査範囲を業務に関連する事項に限定し、必ず候補者本人から書面で同意を得ることが不可欠です。
個人情報の取り扱いに関する法律
バックグラウンドチェックを行う際には、個人情報保護法をはじめとする関連法令を遵守することが不可欠です。
調査を実施する前に、調査の目的・内容・利用範囲を明確に説明し、候補者本人から明示的な同意を得ることが原則となります。
同意の取得方法については、書面・電子署名・メールなど、確認可能な形で残すことが望ましいでしょう。
本人の同意を得ずに調査を行った場合、個人情報保護法第17条(適正取得)や民法上のプライバシー権に抵触する可能性があります。
特に、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などは「要配慮個人情報」として法律上厳格に保護されており、取得する場合には本人の明示的同意が必須です。
これらの情報を同意なく収集・利用することは、原則として違法とみなされます。
また、職業安定法第5条の4では、採用活動を行う企業や職業紹介事業者に対して「業務の目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集してはならない」と定めています。
必要以上に詳細な個人情報を求めることは、法令違反となるおそれがあるため注意が必要です。
法律に違反した場合、行政指導・勧告だけでなく、命令違反に対しては懲役刑や罰金刑が科される可能性もあります。
バックグラウンドチェックを実施する企業は、法令を正しく理解し、適切な手続きを踏んで慎重に調査を進めることが求められます。
誤った情報のリスク
バックグラウンドチェックには、誤った情報が報告されるリスクが常に伴います。調査過程で同姓同名の人物の情報が混入したり、公的記録自体に誤りがあったりした場合、候補者は事実と異なる経歴や評価によって不採用となるなど、重大な不利益を被る可能性があります。
企業側にとっても、このリスクは軽視できません。誤った情報に基づいて採用判断を下せば、本来有望だった人材を逃す機会損失につながるでしょう。さらに、その不採用決定が原因で候補者から訴訟を起こされるケースも考えられます。
こうした事態を避けるためには、信頼性の高い調査会社を選定することが不可欠です。また、調査結果に少しでも疑問が生じた際は、すぐに結論を出すのではなく、候補者本人に事実確認の機会を設けるなど、慎重な対応が求められるのです。
バックグラウンドチェックに関するよくある質問(Q&A)
Q1:バックグラウンドチェックとは何ですか?
A1:採用候補者の経歴・素行・信用状況などを確認し、採用判断の参考にする調査です。学歴・職歴の確認、反社会的勢力との関係確認(反社チェック)、公開されたSNS投稿の確認などが含まれます。
Q2:バックグラウンドチェックは違法ではないのですか?
A2:本人の同意を得て、適法な手段で実施する限り違法ではありません。本人同意なしの収集や、犯罪歴・思想・信条などの要配慮個人情報を無断で調査・利用する行為は法令違反の可能性があります。
Q3:企業はどのような目的でバックグラウンドチェックを行うのですか?
A3:採用後のトラブル防止と企業の信用維持が目的です。虚偽経歴の防止、反社関係の有無確認、金銭管理職での不正防止など、リスクマネジメントの一環として行われます。
Q4:どのような情報が調査されますか?
A4:一般に、学歴・職歴・資格・勤務実績・公開SNS・反社関係の有無などです。金融など一部職種では、本人の同意のもとで、本人開示の信用情報や官報の破産公告などの公開情報を確認する場合もあります。
Q5:調査にはどのくらい期間がかかりますか?
A5:内容によりますが、おおむね数日〜2週間程度です。基本的な経歴確認は数日、複数項目の照会や海外調査を含む場合はさらに長くなることがあります。
Q6:バックグラウンドチェックで不利になるケースは?
A6:経歴詐称、重大な犯罪歴、反社会的勢力との関係、不適切なSNS投稿などが典型例です。ただし、判断は職務との関連性や社内の採用基準に基づいて行われます。
Q7:候補者が調査に同意しなかった場合はどうなりますか?
A7:同意がなければ調査はできません。職務遂行上どうしても必要な確認がある場合は、その必要性を説明したうえで選考を進めるかを判断します。
Q8:調査結果は本人に開示されますか?
A8:法的に一律の開示義務はありませんが、候補者は個人情報保護法に基づき、自身に関する情報の開示・訂正・削除を求めることができます。企業は適切に対応する体制が望まれます。
Q9:調査会社に依頼する際の注意点は?
A9:探偵業法の届出があるか、個人情報の管理体制が整っているか、違法な手段(不正アクセス・盗聴等)を用いないかを確認してください。報告書の根拠や情報源が明示されるかも重要です。
Q10:海外勤務者や外国籍候補者のバックグラウンドチェックも可能ですか?
A10:可能です。ただし国・地域で個人情報保護法制が異なるため、現地法に適合した方法で進める必要があります。国際調査の実績がある事業者に依頼するのが安全です。
バックグラウンドチェックで分かることは何か
バックグラウンドチェックは、採用候補者が申告した経歴に偽りがないか、また企業にとって不利益となるリスクを抱えていないかを確認するために実施されます。具体的には、履歴書や職務経歴書に記載された学歴や職歴が事実と相違ないか、卒業証明書の提出を求めたり、過去の勤務先に在籍期間などを問い合わせたりして確認します。
さらに、公的に公開されている情報を基に、破産歴の有無を官報で調査することもあります。 近年では、候補者のコンプライアンス意識や人物像を把握するため、本人の同意のもとで公開されているSNSの投稿内容を確認するケースも増えています。
そのほか、反社会的勢力との関わりがないかのチェックや、前職の上司や同僚に勤務態度や実績をヒアリングするリファレンスチェックも、調査項目に含まれることがあります。
バックグラウンドチェックの結果が不利になることはあるか
バックグラウンドチェックの結果が、採用選考において不利に働く可能性は十分にあります。
特に、履歴書や職務経歴書に虚偽の記載がある場合や、重大な不正行為が発覚した場合は、候補者の信頼性が損なわれるため、内定取り消しや採用見送りの正当な理由とみなされることが多いです。
(※労働契約法第16条では、「合理的な理由がある場合の内定取消」は有効とされています。)
また、反社会的勢力との関係や重大な犯罪歴が確認された場合も、企業のコンプライアンス遵守義務の観点から採用が難しくなるのが一般的です。
金融機関・教育・医療・警備業界などでは、法令・業界ガイドラインに基づき、社会的信用に関わる人物の雇用は厳しく制限されています。
一方で、個人の破産歴については注意が必要です。
官報に掲載されるため公開情報ではありますが、業務に関連性のない範囲で破産歴を採用判断に利用することは、職業安定法や差別禁止の観点から不当とされる可能性があります。
金銭を直接扱う職務など、職務上の信用が特に重要な場合を除き、破産歴のみで採否を決めるのは避けるべきです。
近年では、SNS上での差別的発言や暴言、社会的モラルに反する投稿が確認され、企業が「企業風土に適合しない」と判断するケースも増えています。
ただし、SNS調査を行う場合は、調査範囲・評価基準・本人同意の有無を明確にしておくことが法的トラブル防止につながります。
最終的に、バックグラウンドチェックの結果が採用にどの程度影響するかは、職務内容と情報の関連性、企業の採用ポリシー、社会的合理性によって判断されます。
企業は、法令を遵守したうえで公平・客観的な基準に基づく判断を行うことが求められます。
\バックグラウンドチェックならPIO探偵事務所へ/
まとめ:バックグラウンドチェックの不安を解消し、最適な方法を見つけよう
今回は、バックグラウンドチェックの実施を検討している方に向け、
– バックグラウンドチェックとは何か
– バックグラウンドチェックの実施方法
– バックグラウンドチェックの注意点
– バックグラウンドチェックのよくある質問
上記について、解説してきました。
バックグラウンドチェックは、採用のミスマッチを防ぐ上で非常に有効な手段です。
しかし、正しい手順を踏まないと法的な問題に発展する可能性もあり、費用も決して安くはありません。
どの調査会社に依頼すれば良いのか、費用はどれくらいかかるのか、不安に感じる方もいるでしょう。
だからこそ、この記事で解説した実施方法や費用の知識が、あなたの会社にとって最適な選択をするための羅針盤となるはずです。
まずは自社が何を重視するのかを明確にすることから始めてみましょう。
より良い人材を採用したい、というその想いは非常に尊いものです。
これまで採用活動で試行錯誤されてきた経験は、決して無駄にはなりません。
適切なバックグラウンドチェックを行うことで、企業の文化に合った優秀な人材と出会える可能性が格段に高まります。
それは、会社の未来をより明るく照らす一歩となるでしょう。
この記事を参考に、ぜひ信頼できるパートナーを見つけ、ミスマッチのない採用を実現してください。
筆者はあなたの会社の成功を心から応援しています。

探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。