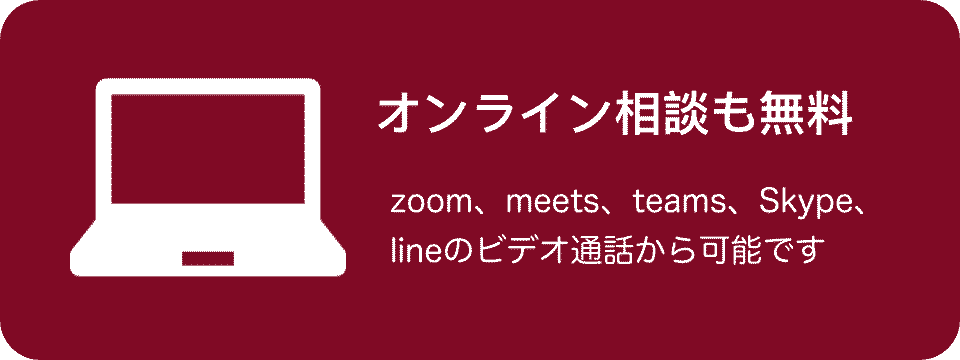【採用調査】どこまでが合法なのか?成功するための完全ガイド!

「採用調査って、どこまで調べていいのだろうか…」と悩む方もいるでしょう。
「合法的に調査を進めたいけれど、何が許されているのか不安…」と心配になることもありますよね。
採用調査は企業にとって重要なプロセスですが、法律や倫理の問題に直面することも少なくありません。
採用調査を成功させるためには、まずは合法的な範囲をしっかりと理解することが大切です。
この記事を読めば、どこまでが許されているのか、どのように調査を進めれば良いのかが分かります。
ぜひ、この記事を参考にして、安心して採用調査を進めてください。
この記事では、採用調査に関心のある方に向けて、
– 採用調査の合法性の範囲
– 採用調査で確認される主な項目
– 採用調査を行う際の重要ポイント
上記について、解説しています。
採用調査における法律や倫理の問題は複雑ですが、このガイドを読むことで安心して調査を進めることができるでしょう。
採用プロセスを円滑に進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
PIO探偵事務所は興信所探偵社として業歴53年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽にPIO探偵事務所までご相談下さい。
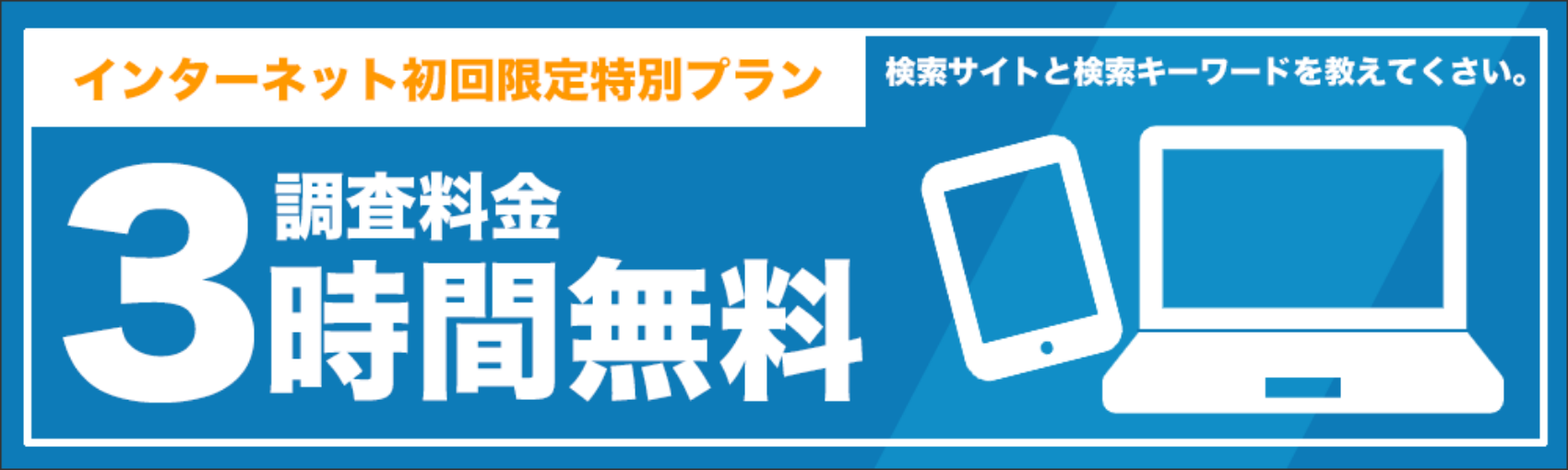
目次
採用調査とは?その目的と必要性
採用調査は、企業が新たな人材を採用する際に、応募者の経歴や適性を詳細に確認するプロセスです。この調査を通じて、履歴書や面接だけでは把握しきれない情報を得ることができ、採用のミスマッチを防ぐ役割を果たします。
企業が採用調査を行う主な目的は、経歴詐称の防止や、過去の職務態度、退職理由などを明らかにし、組織に適した人材を確保することです。特に中途採用では、前職での実績や人間関係が重要視されるため、これらの情報を正確に把握することが求められます。
例えば、前職での退職理由が問題行動によるものであった場合、採用後に同様の問題が発生するリスクがあります。採用調査を実施することで、こうしたリスクを事前に察知し、適切な人材選定が可能となります。
採用調査が行われる背景
採用調査が行われる背景には、企業が適切な人材を確保し、採用後のトラブルを防ぐという目的があります。
近年、日本では労働力不足が深刻化し、特に中途採用市場が活発になっています。
リクルートワークス研究所の「中途採用実態調査(2023年度下半期)」によると、**中途採用を実施した企業は79.5%**に達しており、10年前(59.9%)と比べて大幅に増加しています。
こうした状況の中で、企業は採用後のミスマッチや経歴詐称によるリスクを避けるため、採用調査(バックグラウンドチェック)を重要視する傾向が強まっています。
調査では、応募者の学歴・職歴・資格・反社会的勢力との関係・SNSでの発信内容などを確認し、企業の信頼性や安全性を守ることが目的です。
ただし、調査を行う際には、個人情報保護法や職業安定法、公正採用選考の基本に基づき、適正な手続きで実施しなければなりません。
特に、本人の同意なく犯罪歴や家族構成、思想信条などを調べることはプライバシー侵害や就職差別につながる可能性があります。
このように、採用調査は単なる身辺確認ではなく、企業が法令を遵守しながら組織の健全性を維持するためのリスク管理手段として活用されているのです。
企業が採用調査を実施する理由
企業が採用調査を実施する主な理由は、応募者の経歴や適性を正確に把握し、採用後のミスマッチやトラブルを未然に防ぐことにあります。
近年の日本では人材確保が難しくなっており、リクルートワークス研究所の調査(2023年度)によると、66.6%の企業が「中途採用が難しくなっている」と回答しています。
採用調査では、応募者の学歴・職歴・資格の真偽、および反社会的勢力との関係の有無などを確認することで、企業はより適切な人材を見極められます。
この結果、採用後のトラブルや早期離職を防ぎ、組織の安定性と生産性を向上させることができます。
また、採用調査は企業コンプライアンスの強化にもつながります。応募者が反社会的勢力と関わりを持っていないか、過去に重大な法的トラブルがないかを確認することで、企業の社会的信用やブランド価値の維持に寄与します。
ただし、犯罪歴などの個人情報を調査する場合は、本人の明確な同意が必要であり、警察・検察への照会は行えません。公開情報(官報・報道等)の確認にとどめるのが適法です。
さらに、採用調査は経営戦略と人材戦略を結びつける手段としても重要です。
企業が今後の事業拡大やビジネスモデル転換を進める際、リーダーシップや倫理観、信頼性を備えた人材を見極めるための判断材料としても活用されています。
このように、採用調査は企業が法令を遵守しつつ適切な人材を確保し、組織の健全性と成長を支えるための重要なプロセスとなっています。
採用調査の法的側面
採用調査を実施する際、法的な側面を理解し、適切に対応することが重要です。企業には採用の自由が認められていますが、調査方法や内容によっては法的リスクが生じる可能性があります。
例えば、厚生労働省は公正な採用選考のために、応募者の本籍や家族構成、宗教、支持政党など、本人に責任のない事項や思想信条に関する情報の収集を避けるよう求めています。これらの情報を調査することは、就職差別につながる恐れがあるため、慎重な対応が必要です。
以下で詳しく解説していきます。
個人情報保護法と採用調査
採用調査を行う際、個人情報保護法の遵守が不可欠です。この法律は、個人情報の適正な取り扱いを求め、特に「要配慮個人情報」(例:病歴、犯罪歴、信条など)の取得には本人の同意が必要とされています。
企業が採用調査を実施する場合、以下の点に注意が必要です。
– 利用目的の明確化と通知:個人情報を取得する際、その利用目的をできる限り特定し、本人に通知または公表する必要があります。
– 適正な情報取得方法:偽りや不正な手段で個人情報を取得することは禁止されています。
– 要配慮個人情報の取り扱い:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などの要配慮個人情報を取得する際は、原則として本人の同意が必要です。
これらの規定を遵守しない場合、法的リスクが生じる可能性があります。例えば、本人の同意なく前職調査を行うことは、個人情報保護法違反となる恐れがあります。
採用調査を適法に行うためには、事前に本人の同意を得ること、取得する情報の範囲を明確にすること、そして取得した情報を適切に管理・利用することが求められます。これにより、企業は法的リスクを回避し、信頼性の高い採用活動を実施することができます。
調査内容による就職差別のリスク
採用調査の内容によっては、就職差別につながるリスクが非常に高くなります。
厚生労働省は「公正な採用選考の基本」において、応募者の適性や能力と無関係な情報、すなわち「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項」を把握することは、就職差別の原因となるおそれがあると明確に指摘しています。
具体的には、次のような情報が該当します。
- 本籍地や出生地に関すること
- 家族の職業・学歴・収入など
- 宗教、思想、信条
- 住宅状況や生活環境
これらの情報を採用調査で収集し、採否の判断に利用することは、応募者の人権を侵害し、法的・社会的トラブルを引き起こす可能性があります。
例えば、家族構成や宗教への質問は、本人の意思とは関係のない属性を評価する行為であり、差別的な取り扱いと見なされる場合があります。
また、近年ではSNS調査によるプライバシー侵害リスクにも注意が必要です。
日本労働組合総連合会(連合)の調査によると、**就職活動中にSNSアカウントを企業に調べられたと回答した人は10.7%**に上ります。
SNS上の投稿を選考判断に用いることは、思想・価値観などの「本来自由であるべき事項」を評価に反映させる行為とみなされるおそれがあり、間接的な差別やプライバシー侵害につながる可能性があります。
採用調査を行う際は、応募者の業務遂行能力や職務適性に直接関係する情報のみに焦点を当てることが重要です。
企業は個人のプライバシーと人権を尊重し、法令やガイドラインに基づいて公正な採用選考を行うことで、法的リスクを回避し、社会的信頼性を高めることができます。
内定取り消しに伴う法的リスク
内定取り消しは、企業にとって大きな法的リスクを伴う行為です。
実は「内定」は、将来の入社を前提とした労働契約の一種とみなされています。
つまり、会社が一方的に内定を取り消すことは、契約を一方的に破ることと同じ扱いになる可能性があるのです。
もし正当な理由がないまま内定を取り消した場合、違法と判断されることがあります。
たとえば、企業の都合で採用枠を減らしたり、業績が悪化したという理由だけでは、必ずしも内定取り消しが認められるとは限りません。
違法な内定取り消しを行うと、企業が損害賠償を求められる可能性があります。
内定者が他の就職先を断っていたり、精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料や逸失利益(失った将来の収入)を請求されるケースもあります。
実際に、過去の裁判では100万円以上の賠償命令が出た例もあります。
さらに、厚生労働省では「内定取り消しを行った企業名を公表する制度」を設けています。
違法な取り消しと判断された場合、企業名が発表されることもあり、社会的信用を大きく失うリスクがあります。
一度信用を失うと、新卒採用だけでなく、取引先や顧客にも悪影響が及ぶ可能性があります。
そのため、内定取り消しを検討する場合は、本当にやむを得ない理由があるかを慎重に判断することが大切です。
「経歴詐称があった」「重大な不正行為をした」など、客観的な理由がなければ取り消しは難しいでしょう。
また、トラブルを防ぐためには、内定者と誠実に話し合うこと、そして必要に応じて弁護士など専門家の意見を聞くことが重要です。
採用調査で確認される主な項目
採用調査では、候補者の適性や信頼性を評価するために、以下の主要な項目が確認されます。
学歴や職歴の確認
候補者が提出した履歴書や職務経歴書の内容が正確であるかを検証します。具体的には、卒業証明書の提出を求めたり、前職の在籍期間や職務内容を確認するために、前勤務先に問い合わせを行います。これにより、経歴詐称の有無を明らかにし、候補者の信頼性を確保します。
反社会的勢力との関係チェック
候補者が反社会的勢力と関係を持っていないかを調査します。これは、企業の社会的信用を守るために重要です。具体的には、公開情報や専門データベースを活用して、候補者の過去の関与歴や関連性を確認します。
犯罪歴や訴訟歴の確認
候補者の過去の犯罪歴や訴訟歴を調査し、企業にとってのリスクを評価します。日本では、警察の犯罪歴記録は非公開であるため、官報や公開された裁判記録、インターネット上の情報を活用して確認を行います。
SNSやインターネットでの調査
候補者のSNSやインターネット上の活動を調査し、不適切な発言や行動がないかを確認します。これにより、企業の評判や職場環境に悪影響を及ぼす可能性のある要素を事前に把握できます。具体的には、候補者の名前で検索を行い、公開されている投稿内容や画像をチェックします。
これらの調査項目を通じて、企業は候補者の適性や信頼性を総合的に評価し、採用の判断材料とします。
経歴や職歴の確認
採用調査における経歴や職歴の確認は、応募者の申告内容が正確であるかを検証し、企業のリスクを最小限に抑えるために重要です。しかし、調査を行う際には、個人情報保護法や職業安定法などの法的規制を遵守し、応募者のプライバシーを尊重する必要があります。
具体的な確認方法として、履歴書や職務経歴書の内容を精査し、面接時に詳細を尋ねることが挙げられます。また、応募者の同意を得た上で、退職証明書や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの公的書類を提出してもらうことで、在籍期間や職務内容を確認することが可能です。さらに、リファレンスチェックを通じて、前職の上司や同僚から業務遂行能力や人柄についての情報を得る方法も有効です。
ただし、これらの調査を行う際には、応募者の同意を事前に取得し、調査の目的や範囲を明確に伝えることが求められます。また、調査内容は業務遂行に直接関連する事項に限定し、思想・信条や家族構成など、業務と無関係な個人情報の収集は避けるべきです。これらの配慮を怠ると、プライバシーの侵害や法的トラブルに発展する可能性があります。
経歴や職歴の確認は、企業にとって信頼性の高い人材を採用するための重要なプロセスです。しかし、法的規制を遵守し、応募者の権利を尊重する姿勢が、企業の信頼性を高めることにつながります。
反社会的勢力との関係チェック
採用時における反社会的勢力との関係チェックは、企業の信頼性と安全性を守るために不可欠です。反社会的勢力とは、暴力団やその関係者、詐欺グループなど、社会秩序を乱す組織や個人を指します。
企業がこれらの勢力と関わると、取引先からの契約解除や社会的信用の失墜、最悪の場合、法的制裁を受けるリスクがあります。そのため、採用プロセスにおいて、候補者が反社会的勢力と無関係であることを確認することが求められます。
具体的なチェック方法としては、インターネット検索や新聞記事の確認、専門の調査機関への依頼などがあります。また、候補者に対して反社会的勢力との関係がないことを誓約する書面を提出させることも有効です。
これらの対策を講じることで、企業は反社会的勢力との関与を未然に防ぎ、健全な事業運営を維持することができます。
犯罪歴や訴訟歴の確認
採用調査における犯罪歴や訴訟歴の確認は、企業が候補者の信頼性や適性を評価する上で重要な要素です。しかし、これらの情報は個人のプライバシーに深く関わるため、調査には慎重な対応が求められます。
犯罪歴の確認方法と注意点
日本では、警察が管理する犯罪経歴情報は一般に公開されておらず、企業や調査会社が直接照会することはできません。そのため、公開された新聞記事や裁判所の公開情報を検索することで、犯罪歴を確認する方法が一般的です。ただし、報道されていない軽微な犯罪歴を網羅的に把握することは困難です。また、個人情報保護法では、犯罪歴は「要配慮個人情報」として扱われ、本人の同意なしに取得することは原則として禁止されています。したがって、調査を行う際は、候補者から事前に明確な同意を得ることが不可欠です。
訴訟歴の確認方法と注意点
訴訟歴の確認も、公開された裁判記録や新聞記事を通じて行われます。しかし、すべての訴訟が報道されるわけではなく、情報の入手には限界があります。また、訴訟歴も個人情報に該当するため、調査を行う際は候補者の同意が必要です。無断での調査は、プライバシーの侵害や法的リスクを伴う可能性があります。
調査の適法性とリスク管理
企業が犯罪歴や訴訟歴を理由に採用を見送る場合、その判断が業務遂行能力や職務適性に直接影響を及ぼすものでなければ、差別とみなされるリスクがあります。例えば、金融機関や警備業など、高い信用性が求められる職種では、これらの調査が正当化される場合がありますが、他の職種では慎重な判断が求められます。調査を行う際は、業務との関連性を十分に検討し、必要最小限の範囲で実施することが重要です。
まとめ
犯罪歴や訴訟歴の確認は、企業のリスク管理において重要な役割を果たしますが、個人情報保護法やプライバシーの観点から、調査の実施には慎重な対応が求められます。候補者の同意を得ること、業務との関連性を明確にすること、そして調査結果の取り扱いに注意を払うことが、適法かつ効果的な採用調査を行う上で不可欠です。
SNSやインターネットでの調査
採用調査において、候補者のSNSやインターネット上の情報を確認することは、近年一般的になりつつあります。しかし、この手法には慎重な対応が求められます。
まず、SNS上の情報は個人のプライベートな側面を反映しており、これを無断で調査することはプライバシーの侵害となる可能性があります。実際、連合の調査によれば、採用選考過程で企業からSNSアカウントを調査された経験があると回答した人は10.7%に上ります。 このような調査は、候補者の信頼を損なうだけでなく、法的な問題を引き起こすリスクも伴います。
さらに、SNS上の情報は必ずしも正確でない場合があり、誤解や偏見を生む原因となることも考えられます。例えば、候補者がプライベートで投稿した内容が、企業文化や価値観と合わないと判断され、不採用の理由となるケースも報告されています。
このようなリスクを避けるため、企業は候補者の同意を得た上で、採用に直接関連する情報のみを調査対象とすることが望ましいでしょう。また、調査結果の活用に際しては、客観的かつ公平な判断を心がけることが重要です。
要するに、SNSやインターネット上の情報を採用調査に活用する際は、プライバシーの尊重と法的リスクの回避を最優先に考え、慎重に対応することが求められます。
採用調査を行う際の重要ポイント
採用調査を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえることが不可欠です。まず、調査を行う際には、候補者の同意を得ることが法的に求められます。これにより、個人情報保護法に準拠し、信頼関係を築くことができます。
次に、調査項目の選定が重要です。企業のニーズに合わせて、学歴や職歴、犯罪歴、反社会的勢力との関係など、必要な情報を明確に定めることで、効率的かつ効果的な調査が可能となります。
さらに、調査結果の活用方法も考慮すべきです。得られた情報をもとに、候補者の適性やリスクを総合的に評価し、採用の最終判断に役立てることが求められます。
調査を行う最適なタイミング
採用調査を行う最適なタイミングは、候補者の選考段階や企業の採用プロセスによって異なりますが、一般的には内定を出す前、最終面接後が適切とされています。この時期に調査を実施することで、候補者の経歴や適性を最終的に確認し、採用の可否を判断する材料とすることができます。
また、企業の採用活動は年間を通じて行われますが、特に新年度が始まる4月に向けて、1月から3月にかけて採用活動が活発化する傾向があります。この時期に合わせて採用調査を計画することで、より多くの候補者と接触し、適切な人材を見極めるチャンスが増えるでしょう。
さらに、企業によっては、スポットワークや短期バイトを通じて候補者の働きぶりを確認し、その後長期採用を検討するケースも増えています。この方法では、実際の業務を通じて候補者の適性や職場への適応度を評価できるため、採用調査の一環として有効です。
採用調査のタイミングを適切に設定することで、企業は候補者の情報を正確に把握し、ミスマッチを防ぐことが可能となります。これにより、採用後の定着率向上や早期離職の防止にもつながるでしょう。
効果的な調査項目の選定
採用調査を成功させるためには、調査項目の選定が極めて重要です。適切な項目を選ぶことで、候補者の適性やリスクを正確に評価し、企業にとって最適な人材を見極めることができます。
まず、候補者の経歴や職歴の確認は基本中の基本です。履歴書や職務経歴書の内容が正確であるかを検証し、過去の職務経験や実績を把握することで、業務遂行能力や適性を判断できます。
次に、反社会的勢力との関係チェックも欠かせません。候補者が反社会的勢力と関わりがないかを確認することで、企業の社会的信用を守ることができます。
さらに、犯罪歴や訴訟歴の確認も重要です。候補者が過去に法的な問題を抱えていないかを調査することで、将来的なリスクを未然に防ぐことが可能となります。
また、SNSやインターネットでの調査も有効です。候補者の公開された情報から、価値観やコミュニケーションスタイル、過去の発言内容などを把握し、企業文化との適合性を判断できます。
これらの調査項目を適切に選定し、バランスよく組み合わせることで、採用リスクを最小限に抑え、企業にとって最適な人材を確保することが可能となります。
調査結果の適切な活用法
採用調査の結果を適切に活用するためには、以下のステップが重要です。
1. 調査結果の分析と課題の特定
まず、収集したデータを詳細に分析し、応募者の経歴や職歴、スキルセット、適性などを評価します。これにより、採用基準に合致する候補者を特定しやすくなります。例えば、特定のスキルや経験が不足している場合、その分野での研修や教育プログラムの導入を検討することができます。
2. 採用プロセスの改善
調査結果から、選考プロセスの各段階での通過率や辞退率を算出し、どのフェーズで問題が発生しているかを特定します。例えば、一次面接での辞退率が高い場合、面接手法や内容の見直しが必要かもしれません。これにより、選考プロセス全体の効率化と質の向上が期待できます。
3. 採用戦略の見直し
調査結果を基に、採用チャネルや募集方法の効果を評価し、最も効果的な手法にリソースを集中させます。例えば、特定の求人媒体からの応募者の質が高い場合、その媒体への投資を増やすことで、より適切な人材の確保が可能となります。
4. フィードバックと改善策の実施
調査結果を社内で共有し、関係者からのフィードバックを収集します。その上で、具体的な改善策を策定し、実施に移します。例えば、従業員満足度調査の結果を活用して、職場環境の改善や研修プログラムの充実を図ることができます。
5. 継続的なモニタリングと評価
改善策の効果を定期的に評価し、必要に応じてさらなる調整を行います。これにより、採用活動の質を持続的に向上させることができます。
以上のプロセスを通じて、採用調査の結果を効果的に活用し、組織の成長と発展に寄与することが可能となります。
採用調査の方法と選択肢
採用調査を実施する際、企業は主に以下の方法を選択できます。
自社での調査実施: 企業自身が候補者の経歴や職歴を確認する方法です。この手法はコストを抑えられますが、調査範囲が限定的で、専門的な情報収集が難しい場合があります。
探偵や調査会社の利用: 専門の調査機関に依頼することで、候補者の詳細なバックグラウンドチェックが可能となります。これにより、反社会的勢力との関係や犯罪歴など、より深い情報を得ることができます。ただし、費用が高額になることや、調査の合法性を確認する必要があります。
リファレンスチェックサービスの活用: 候補者の前職の上司や同僚から直接評価を得る方法です。これにより、職務能力や人間関係の適性を把握できます。ただし、提供される情報が主観的である点や、前職の協力が得られない場合がある点に注意が必要です。
各方法にはメリットとデメリットが存在するため、企業のニーズやリソースに応じて最適な手法を選択することが重要です。
自社での調査実施
自社で採用調査を実施する際は、コスト削減や自社のニーズに合わせた柔軟な対応が可能という利点があります。しかし、個人情報保護法などの法的規制を遵守し、調査対象者の同意を得ることが必須です。
また、前職調査では、個人情報保護の観点から情報提供を断られるケースが多く、調査の難易度が高まっています。
さらに、調査の手間や時間、法的リスクを考慮すると、自社での実施には慎重な判断が求められます。これらの点を踏まえ、必要に応じて専門の調査会社への委託も検討することが望ましいでしょう。
探偵や調査会社の利用
採用調査を外部の探偵や調査会社に依頼することは、候補者の経歴や素行を詳細に把握する有効な手段です。これらの専門機関は、尾行や聞き込みなどの手法を用いて情報を収集し、企業に報告します。
しかし、調査の際には「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)を遵守する必要があります。この法律は、探偵業務の適正な運営を確保し、個人の権利や利益を保護することを目的としています。具体的には、調査結果が犯罪行為や違法な差別的取り扱いに利用されることを知った場合、探偵業者はその業務を行ってはならないと定められています。
また、個人情報保護法により、思想や信条、病歴などの「要配慮個人情報」の収集や利用には特に注意が必要です。これらの情報を不適切に扱うと、法的な問題に発展する可能性があります。
さらに、調査対象者のプライバシーを尊重し、違法な手段(例えば、盗聴や不法侵入)を用いないことが求められます。違法な調査方法を採用すると、企業自身が法的責任を問われるリスクがあります。
したがって、探偵や調査会社を利用する際は、これらの法律や規制を十分に理解し、信頼できる業者を選定することが重要です。適切な調査を行うことで、企業は採用のミスマッチを防ぎ、健全な職場環境を維持することができます。
弁護士協同組合特約店だから安心|PIOの採用調査について相談する >
探偵や調査会社の利用とリスク回避
専門の調査機関(探偵事務所や興信所)に依頼することは、候補者の経歴や背景を深く正確に把握する有効な手段です。しかし、業者選びを間違えると、違法調査に巻き込まれ、企業側が法的責任を問われるリスクがあります。
違法業者を見極めるポイント
安全に調査を依頼するために、以下の基準を満たしているか必ず確認してください。
- 探偵業届出標識の有無:公安委員会への届出番号が公式サイトや事務所に掲示されているか。
- 契約の透明性:「口約束」ではなく、契約書に調査内容・期間・料金・手法が明記されているか。
- 違法調査の提案がないか:盗聴、盗撮、住居侵入、差別につながる身元調査など、違法な手段を提案してくる業者は避けてください。
信頼できる調査会社の選び方
トラブルを避けるために、以下のチェックリストを活用しましょう。
- 料金体系が明確か:追加料金の発生条件などが事前に説明されていること。
- 弁護士協同組合特約店か:弁護士と連携している調査会社は、コンプライアンス意識が高く安全です。
- 報告書の質:裁判資料としても使えるレベルの証拠能力があるか(サンプルを見せてもらうと良いでしょう)。
「安すぎる」業者や「どんなことでも調べられる」と豪語する業者はリスクが高いため注意が必要です。
外部委託(探偵・調査会社)のメリット・デメリット
自社調査と比較した場合の、外部委託の特徴を整理しました。
| メリット | 専門的な情報収集力:独自のノウハウで、表面化しにくいリスク(隠れた経歴や風評)を確認できる。 法令遵守(コンプライアンス):プロの調査会社は法律の範囲内で調査を行うため、企業側の法的リスクを低減できる。 客観的な証拠:事実に基づいた報告書が得られ、社内の採用判断がスムーズになる。 |
|---|---|
| デメリット | 費用の発生:1名あたり数万円〜のコストがかかる。 調査の限界:合法的な範囲に限られるため、個人の思想や完全なプライベートまでは調査できない(すべきではない)。 |
リファレンスチェックサービスの活用
リファレンスチェックとは、採用候補者の前職の上司や同僚など第三者にヒアリングを行い、職務実績や人柄を客観的に確認する手法です。
面接や履歴書だけでは分からない「実際の働きぶり」や「チームでの評価」を把握できるため、採用のミスマッチ防止に役立ちます。
日本国内でも近年導入が進んでおり、**外資系企業の約58%、日系企業の約23%**が何らかの形でリファレンスチェックを実施しています(出典:HR総研・BizReach「採用実態調査2023」)。
特に、管理職や専門職など、採用コストが高く再採用が難しいポジションでの導入が目立ちます。
リファレンスチェックには、次のようなメリットがあります。
面接だけでは分からない実務能力や評価の裏付けが取れる
候補者の経歴・実績の正確性を確認できる
企業文化やチームへの適応性を予測できる
ただし、リファレンスチェックを行う際には、候補者本人の同意が必須です。
同意を得ずに前職の関係者へ問い合わせることは、個人情報保護法に抵触するおそれがあります。
また、取得した情報の扱いにも注意が必要で、目的外利用や社外への漏えいは厳禁です。
さらに、リファレンス情報はあくまで採用判断の一つの参考材料として扱うのが望ましいとされています。
一部の意見や主観的な評価だけで不採用を決定することは、公平性を欠くリスクがあるためです。
リファレンスチェックサービスを活用することで、採用プロセスの透明性と信頼性が高まり、企業と候補者の双方にとって納得感のある採用活動を実現できます。
採用調査に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 採用調査(バックグラウンドチェック)とは?
A1. 応募者の学歴・職歴・資格・適法な範囲の信用情報・反社会的勢力との関係などを、本人同意のもとで確認し、ミスマッチやトラブルを未然に防ぐための調査です。
Q2. どこまでが合法で、どんな調査が違法ですか?
A2. 合法なのは、職務適性に必要な範囲(学歴・職歴・資格等)を同意取得後に確認することです。違法または不適切なのは、本籍地・家族構成・宗教・支持政党・思想信条・健康情報など本人の責任や業務適性と無関係な事項の取得、または違法手段(不正アクセス・戸籍等の不正取得)です。
Q3. 同意なしで実施するとどうなりますか?
A3. 本人の明示的な同意なしに個人情報を収集すると、個人情報保護法違反にあたるおそれがあり、法的リスクと信用失墜につながります。書面や電子署名等で明確な同意を取得してください。
Q4. 採用調査の対象項目は何ですか?
A4. 代表例は、学歴・職歴の真偽確認/資格・免許の有効性/在留資格(必要職種のみ)/反社会的勢力との関係(公開情報)/公開範囲のSNS発信内容などです。犯罪歴の警察照会はできません(公開情報や本人提出資料に限定)。
Q5. SNS調査は合法ですか?
A5. 公開範囲の閲覧自体は違法ではありません。ただし、思想・信条等の評価に用いると差別的取り扱いのリスクがあります。職務関連の逸脱行為など明確な基準に限定し、記録の保管・共有も最小限にしてください。
Q6. リファレンスチェック(前職照会)は可能ですか?
A6. 可能です。候補者の事前同意を得たうえで、照会先・質問範囲(職務内容・成果・行動特性等)を明示し、公平な質問票で実施します。私生活や差別につながる事項は質問しません。
Q7. 採用調査はいつ実施するのが安全ですか?
A7. トラブル回避の観点から、最終選考〜内定前に同意を得て実施するのが一般的です。内定後の取消しは法的リスクが大きいため、事前実施が安全です。
Q8. 採用調査の結果はどのように保管・破棄すべき?
A8. 目的外利用を避け、アクセス権限を限定し、必要最小限の期間にとどめます。不採用者の情報は速やかな削除・破棄が原則です。保存が必要な場合も、期間と目的を明確化します。
Q9. 外部の探偵・調査会社に依頼できますか?
A9. 依頼自体は可能ですが、探偵業法の届出を行う適正事業者を選定し、違法手段の提案・実施を行わないことを契約で明確化します。同意取得・調査範囲・報告書の取扱いを契約書に明記しましょう。
Q10. 海外学歴・海外勤務の確認はどう進めますか?
A10. 海外の教育機関・雇用主への照会は、候補者同意と各国の個人情報法制に配慮して実施します。学位証明の第三者認証(例:英文卒業証明・発行機関の認証サービス等)も有効です。
採用調査の費用はどのくらいか?
採用調査の費用は、調査内容や対象者の役職、調査機関によって大きく異なります。一般的な採用調査では、1人あたり3万~5万円程度が相場とされています。しかし、役職者や重要なポストを対象とした詳細な調査では、1人あたり10万~20万円程度の費用がかかることもあります。
また、調査会社によっては、調査期間や内容に応じて料金が設定されており、例えば、一般的な採用調査で48,000円、より綿密な調査で63,000円~100,000円といった料金体系を採用している場合もあります。
このように、採用調査の費用は多様な要因によって変動するため、具体的なニーズに合わせて調査会社と相談し、適切なプランを選択することが重要です。
具体的な料金相場や、調査の詳しい流れについては、以下の総合解説記事で詳しく紹介しています。
▼ 料金や実施フローの詳細はこちら
【採用調査とは】失敗を防ぐ実施方法と料金相場・注意点を完全ガイド >
どのような調査が違法になるのか?
採用調査では、応募者の情報を集める際に法律上の制限があります。
調査の内容によっては、個人の権利を侵害したり、就職差別につながるおそれがあるため注意が必要です。
以下は、違法または不適切とされる代表的な調査項目です。
1. 本人の責任ではない事項の調査
応募者の本籍地・出生地・家族構成・住宅環境などは、本人の努力や能力とは関係のない情報です。
これらを採用判断に用いることは、差別的な扱いにつながるおそれがあり、厚生労働省のガイドラインでも明確に禁止されています。
2. 本人の自由に関する事項の調査
宗教や支持政党、思想・信条、労働組合への加入状況など、個人の内心や信条に関する質問は「本来自由であるべき事項」に該当します。
これらを尋ねたり、調査の参考にしたりすることは、プライバシーの侵害や人権侵害に当たる可能性があります。
3. 医療・健康に関する情報の調査
応募者の健康状態や病歴、障がいの有無といった情報は、「要配慮個人情報」として法律で特に厳しく守られています。
本人の明確な同意なしに取得することは、個人情報保護法に違反するおそれがあります。
入社前に健康診断書を提出させる場合でも、採用可否に直結させる行為は慎重でなければなりません。
4. 違法な手段による情報収集
行政書士や第三者を介して戸籍情報・住民票情報などを不正に入手する行為は、戸籍法・刑法・個人情報保護法などに違反します。
このような違法調査は、企業だけでなく関係者にも刑事責任が及ぶ場合があります。
これらの不適切な調査を行うと、企業は法的な罰則を受けるだけでなく、社会的信用を失うリスクも高まります。
採用調査を実施する際は、職務に関連する範囲内で、正当な目的と方法によって行うことが何より重要です。
調査結果が不採用に影響するのか?
採用調査の結果が不採用に直接影響するかどうかは、調査内容とその活用方法によって異なります。企業が候補者の経歴や職歴、反社会的勢力との関係、犯罪歴、SNSでの発信内容などを調査し、これらの情報が企業の求める人物像や社内規定に合致しない場合、不採用の判断材料となることがあります。
しかし、調査結果をどのように評価し、採用判断に活用するかは企業の方針や基準によって異なります。例えば、過去の軽微な違反歴があっても、現在の能力や適性が高ければ採用されるケースもあります。一方で、企業の価値観や業務内容に照らして重大な問題と判断される場合は、不採用となる可能性が高まります。
また、調査結果を不採用の理由とする際には、個人情報保護法や労働関連法規を遵守し、差別的な取り扱いを避けることが求められます。違法な調査や不適切な情報の利用は、法的リスクを伴うため注意が必要です。
要するに、採用調査の結果が不採用に影響するかどうかは、調査内容、企業の評価基準、法的遵守の観点から総合的に判断されるべきです。
まとめ:採用調査の合法性と成功の秘訣
今回は、採用調査に関心を持つ方に向けて、
– 採用調査の合法性の範囲
– 採用調査で確認される主な項目
– 採用調査を行う際の重要ポイント
上記について、解説してきました。
採用調査の合法性を理解することは、企業にとって非常に重要です。法律を遵守しながら採用活動を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。採用に関する法律や規制は複雑で、時に不安を感じる方もいるかもしれませんが、その理解が成功の鍵となります。
採用調査を成功させるためには、まず法律をしっかりと確認し、適切な手順を踏むことが必要です。これにより、企業の信頼性を高め、優秀な人材を引き寄せることが可能になります。
これまでの努力や調査活動は決して無駄ではありません。その経験は、より良い採用活動に必ず役立つでしょう。
今後も採用調査を続けることで、より良い結果を得られる可能性があります。前向きな姿勢で取り組んでみてください。
具体的には、専門家の助言を求めたり、最新の法律情報を常にチェックすることで、採用調査の成功を確実なものにしていきましょう。あなたの成功を心から応援しています。

PIO探偵事務所編集部監修
本記事はPIO探偵事務所の編集部が企画・編集・監修を行いました。