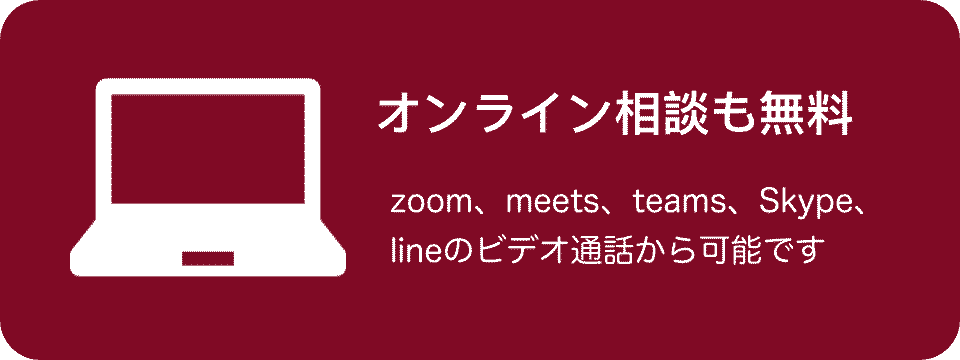怪文書が届いた場合の対処法とは?怪文書の違法性

知らない相手から送られてくる「怪文書」は、相手に対して恐怖を与え、場合によっては生活に支障を与えるような被害をもたらすこともあります。しかし、怪文書だけでは対応策が限られてしまうこともあり、納得のいかない状況になってしまうということも少なくありません。
そこで、今回の記事では、怪文書が届いた場合の対処法と、怪文書の違法性について解説します。
浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください
株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。
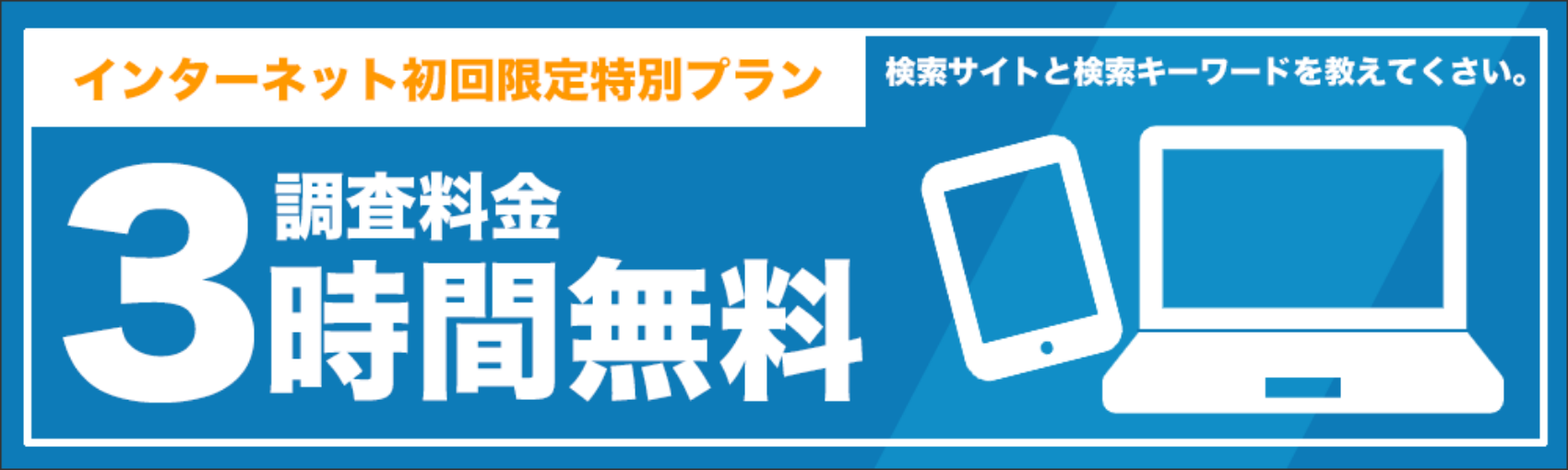
目次
怪文書の違法性について
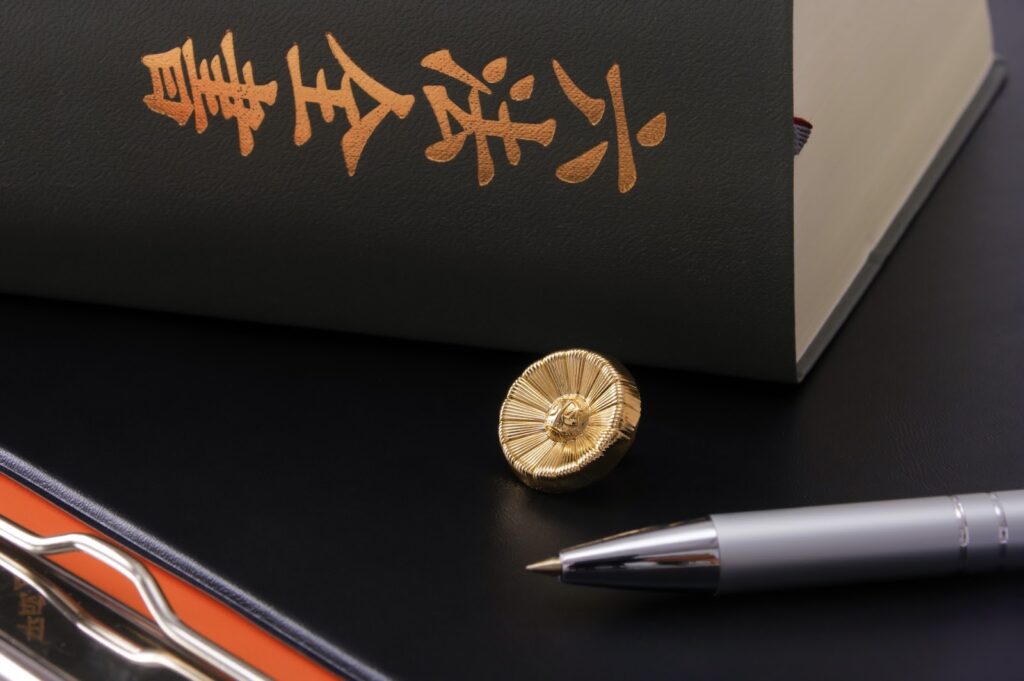
怪文書で相手を陥れることは、明確な犯罪行為に見えますが、実際には違法行為として起訴できる部分は限られており、状況によっては起訴が難しくなってしまうことも少なくありません。
ここでは怪文書が、どのような法律に抵触する可能性があるのか、その違法性について詳しく解説します。
怪文書の違法性1 名誉毀損罪
名誉毀損罪(※1)とは、「公然と事実を摘示して、人の名誉を損する行為」に対する罪で、不特定多数の人物、または閲覧者に具体的な事実を公開(嘘、真実どちらの場合でも)した場合に適用される罪で、知られたくない事実やデマを多くの人に公開された場合などに被害者が訴えるものとなっています。
企業や業者に向けた怪文書の場合は名誉毀損の要件に当てはまることが多いため、被害者が訴えるということがありますが、個人に向けた怪文書の場合は、「不特定多数」に見られる環境という点で合致しないので難しいところがあります。
※1 法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処される
怪文書の違法性2 侮辱罪
侮辱罪(※2)は、「事実を摘示していなくても公然と人を侮辱した行為」に対する罪で、内容が具体的ではなく、相手の誹謗中傷のみの場合でも該当し、不特定多数派もちろん、少数であっても他に広がる可能性がある(ネット上の書き込み)場合は侮辱罪として訴えることができます。
侮辱罪の場合は、企業、個人、どちらの場合でも該当する可能性が高いと言えます。ただし、侮辱罪の公訴時効は、これまで1年とされていましたが、令和4年の改正により3年となりました。怪文書が届いてから3年以内に起訴しなければならないという点に注意する必要があります。
※2 法定刑:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金、又は拘留もしくは科料
ネットを使った怪文書の違法性について
最近では、ネットニュースを装った怪文書やSNSを駆使した怪文書などが使われており、悪質なものが多くなってきています。
ネットを利用した怪文書は「不特定多数の人物が閲覧できる」媒体であることも多く、名誉毀損や侮辱罪といった罪に問われる可能性が高くなります。場合によっては逮捕される可能性もあると言えるでしょう。
怪文書を受け取った際の初期対応

怪文書を受け取った場合、冷静に対応することが非常に重要です。以下に、適切な初期対応の手順を解説します。
冷静さを保つ
怪文書を受け取った際には、感情的に反応せず、冷静に対処することが最も大切です。すぐに公開したり拡散したりせず、事実確認や法的措置を考慮した行動が求められます。
証拠を保全する
怪文書は重要な証拠となるため、適切に保管することが不可欠です。
- 文書に直接触れる際は、手袋を着用し、指紋や DNA を残さないよう注意します。
- 文書を封筒ごと保管し、原本の状態を維持します。
デジタル形式の場合は、スクリーンショットやファイルをバックアップし、保存することを優先します。
- スクリーンショットや印刷で内容を記録する
- メールやSNSのやり取りを保存する(メールヘッダーや送信元の情報も含む)
詳細を記録する
怪文書に関する以下の情報を詳細に記録しましょう。
- 受け取った日時と場所
- 文書の形態(手紙、メール、SNSメッセージなど)
- 文書の内容の要約
- 気づいた特徴や違和感
これらの記録は、後の調査や法的措置の際に重要な情報となります。
関係者への連絡を控える
怪文書の内容について、むやみに他人に話すことは避けましょう。情報が拡散すると、事態が複雑化する可能性があります。まずは専門家に相談することを優先します。
専門家に相談する
怪文書の内容や状況に応じて、以下の専門家に相談することを検討しましょう。
- 弁護士
法的アドバイスや対応策の相談 - 警察
犯罪性が高い場合の相談や被害届の提出 - 探偵事務所
調査や証拠収集の依頼
専門家の助言を得ることで、適切な対応策を立てることができます。
セキュリティ対策の見直し
怪文書が届いた経緯を考え、必要に応じてセキュリティ対策を強化しましょう。
- 自宅や職場のセキュリティシステムの確認
- パスワードの変更
- SNSやオンライン上の個人情報の見直し
これらの初期対応を適切に行うことで、怪文書による被害を最小限に抑え、効果的な対策を講じる基盤を整えることができます。冷静さを保ち、証拠を適切に保全することが、問題解決への第一歩となります。
怪文書が届いた際にやるべきこと

怪文書を送る行為だけで犯人を逮捕することはできません。まずは届いたものを確認し、今後どのような対応をするのか事前に準備しておく必要があります。
警察に相談する
怪文書を告訴する場合は警察に被害届を出すことになるため、まずは警察に相談するのがいいでしょう。警察では怪文書に対する相談が多く寄せられているので、それらの経験を活かし、怪文書の内容で緊急性の高いものか、問題のないものかを確認し、適切な対応方法を助言してくれます。
また、怪文書の犯人が予めわかっている場合であれば、警察から犯人側に警告や説得といった対応(刑罰法令に触れていない場合)をしてくれることもあります。
被害届を出す
怪文書が悪質で、今後もエスカレートする可能性がある場合は警察で被害届を出すようにしましょう。被害届の提出には身分証明書と印鑑が必要になるため、警察に相談する段階で持っていくようにするといいでしょう。
基本的には警察に相談して、被害届が受理できる状況であれば被害届を出すという流れになる傾向です。極度に悪質性や違法性が高い怪文書であれば、即時に被害届を出すことも可能です。
警察に相談する場合は違法行為の証拠を集めておく
警察では、怪文書に対する相談を受け付けてはいるものの、以下のような場合には対応してくれないこともあります。
- 犯人情報がほとんどなく、特定が非常に難しい
- 事件性が低い
- 証拠が不十分で立件が困難な案件
- 違法性を示す証拠が少なすぎる
これは怪文書に限らず、警察の場合は上記のような問題がある場合は対応できないということがあります。こうした場合には、他の機関を紹介してもらったり、個人で別の機関に対応を依頼する必要があります。
怪文書の分析と送り主の特定
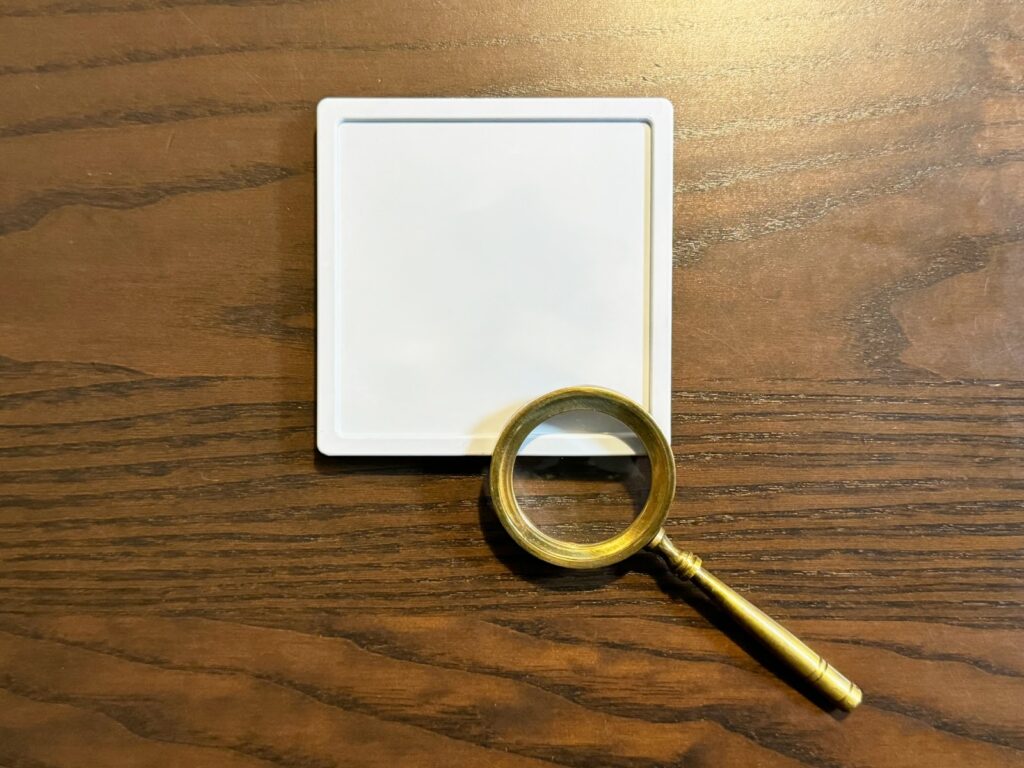
怪文書の分析と送り主の特定は、適切な対応策を講じるための重要なステップです。専門的な知識や技術が必要な場合もあるため、必要に応じて専門家の助けを借りることが効果的です。
内容の詳細な分析
怪文書の内容を詳細に分析することで、送り主の意図や背景、さらには個人を特定できる手がかりを見つけられる可能性があります。文章の特徴や使用される情報から、送り主の属性や動機を推測することができます。
- 文面の特徴(語彙、文体、誤字脱字など)を注意深く観察する
- 内容から送り主の知識や背景を推測する
- 特定の個人しか知り得ない情報が含まれていないか確認する
物理的な証拠の確認
紙媒体の怪文書の場合、物理的な特徴から多くの情報を得ることができます。これらの証拠は、法的措置を取る際にも重要な役割を果たす可能性があります。
- 手書きの場合は筆跡を分析する(専門家への依頼も検討)
- 印刷物の場合は使用された紙や印刷方法を確認する
- 封筒や切手、消印などから発送地や日時を特定する
デジタルフォレンジック
電子媒体を通じて送られてきた怪文書の場合、デジタルフォレンジックの技術を用いることで、送信元や送信者に関する重要な情報を得られる可能性があります。ただし、専門的な知識が必要なため、専門家に依頼することが推奨されます。
- 電子メールの場合はヘッダー情報を分析する
- SNSや掲示板の投稿であれば、IPアドレスや投稿パターンを調査する
専門家への相談
怪文書の分析や送り主の特定には専門的な知識や技術が必要な場合が多いため、適切な専門家に相談することが重要です。専門家の助言を得ることで、より効果的な対応策を立てることができます。
- 探偵事務所や法律専門家に相談し、デジタル怪文書などの専門的な分析や助言を受ける
- 必要に応じて筆跡鑑定や指紋鑑定などの科学的分析を依頼する
関係者への聞き込み
怪文書の内容から関係者が推測できる場合、慎重に聞き込みを行うことで有用な情報を得られる可能性があります。ただし、プライバシーの侵害や二次被害のリスクもあるため、十分な配慮が必要です。
- 内容から推測される関係者に慎重に聞き込みを行う
- ただし、怪文書の存在を不必要に広めないよう注意する
- 疑わしい人物の身辺調査を探偵に依頼する
証拠の保全
怪文書は重要な証拠となるため、適切に保全することが極めて重要です。証拠の保全方法を誤ると、後の法的措置や調査に支障をきたす可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に行う必要があります。
- 怪文書の原本を適切に保管し、証拠として使用できるようにする
- デジタルデータの場合は改ざんされないよう注意する
組織としての対応

怪文書が組織に届いた場合、個人の問題ではなく、組織全体で対応することが非常に重要です。迅速かつ計画的に対応することで、被害の拡大を防ぎ、信頼を守ることができます。以下は、組織として取るべき対応のポイントです。
危機管理チームの編成
社内での対応を統括する危機管理チームを編成します。このチームには、広報担当、法務担当、人事担当などの主要メンバーが参加し、怪文書に対する一貫した対応方針を立てます。
事実確認と調査
怪文書に記載されている内容が事実かどうか、社内で徹底的に確認します。事実と異なる場合、迅速に虚偽であることを証明できる証拠を集めます。逆に、事実が含まれる場合は、対応策を速やかに講じる必要があります。
社内外への情報発信
怪文書が外部に拡散される前に、適切な対応として社内外へのコミュニケーションを確立することが重要です。特に、社内の従業員には事実関係を速やかに説明し、冷静な対応を促します。また、外部に対しても、広報やメディア対応を通じて、信頼を保つためのメッセージを発信します。
法的措置の検討
怪文書が名誉毀損や誹謗中傷に該当する場合、法的措置を検討します。弁護士や法務部門と協力し、必要に応じて法的な対応や損害賠償の請求を進めます。また、SNSなどを利用した怪文書の場合は、プラットフォームへの削除依頼や情報開示請求も含め、問題の迅速な解決を目指します。
内部統制の強化
怪文書が組織内の問題に関わる場合、その発生背景を検討し、内部統制の強化を図ります。従業員教育や内部告発制度の整備、情報管理体制の見直しなどを通じて、再発防止に取り組むことが重要です。
メディア対策と広報戦略
メディアで怪文書の内容が取り上げられる場合、組織としての対応方針を明確にし、一貫した広報戦略を実施します。正確な情報を発信し、組織の信頼性を維持するための適切な対応を行います。
怪文書に対する組織の対応は、危機管理能力が問われる重要な局面です。迅速にチームを編成し、事実確認から法的措置、広報まで一貫した対応を取ることで、被害を最小限に抑えることが可能です。
警察が対応してくれなかった場合の対処法

証拠が少ない、犯人特定が難しい、事件性が低いなどの理由で警察から対応してもらえない場合は、他の機関に依頼して怪文書の犯人特定に役立てることができます。
探偵事務所や興信所に相談する
探偵事務所によっては、怪文書の調査を専門で行っている場合もあり、警察が動けないという案件でも犯人特定や違法性の調査などが可能です。また、怪文書調査から他の情報が得られる可能性もあるため、結果的に複数の問題を解決できることもあります。
また、探偵事務所が筆跡鑑定に対応している、又は筆跡鑑定事務所と連携していることもあるので、怪文書の筆跡から相手を特定するということができる可能性もあります。
警察へ相談すると同時に探偵や興信所に相談することも選択肢の一つといえます。
弁護士に相談する
告訴を検討しているのであれば、法律に詳しい弁護士に相談することが最も効果的です。また、弁護士の中には探偵事務所と連携しているところもあるため、探偵の調査と連動して弁護士に相談することができれば、さらに詳細な情報を得られる可能性があります。
まとめ

今回は怪文書の違法性と、怪文書が送られた場合の対処法について解説しました。記事をまとめると以下のようなことが言えます。
- 怪文書は違法性が高く、刑事責任を問うことができる
- 怪文書が送られてきたら、まずは警察に相談する
- 警察で対応できないなら探偵や弁護士に相談して解決する
怪文書は違法性の高い悪質な行為ではありますが、最近では違法にならないギリギリのラインを利用した怪文書が送られてくるケースも多く、本人だけで判断するのは難しいと言えます。怪文書が届いたら、まずは警察に相談し、状況に応じて探偵や弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。
PIO探偵事務所は弁護士協同組合特約店の探偵興信所として、年間12,000件の探偵業務を行っています。ご相談や費用のお見積りは無料です。不安やお悩みはメールやお電話でも承ります。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K
調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。